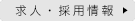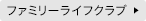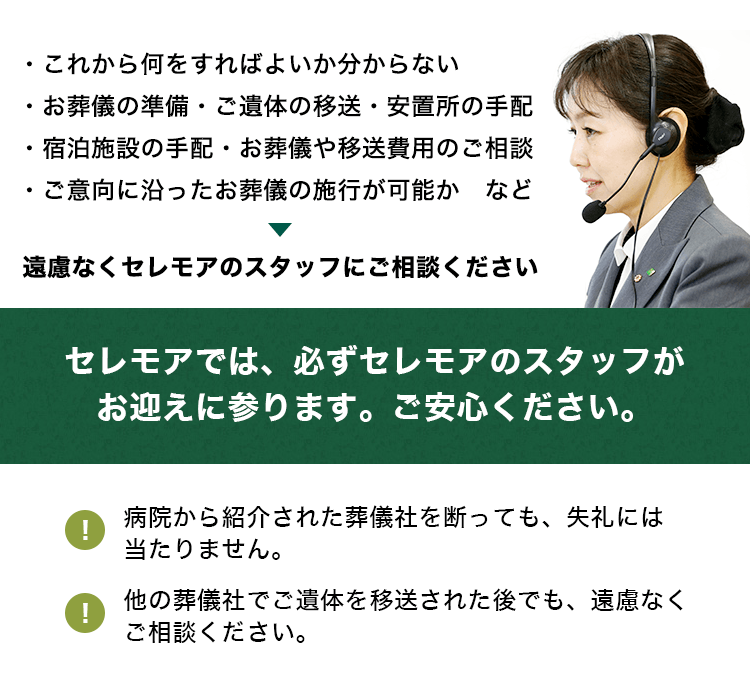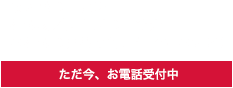家族葬の香典返し|時期・品物の相場・挨拶状の基本マナー
最終更新:2025-08-30
家族葬は、近しい親族や友人のみで執り行われる小規模な葬儀です。
近年、故人との最期の別れをゆっくり過ごしたいという理由から、家族葬を選ぶ方が増えています。
しかし、家族葬における香典返しについては、一般葬とは異なるマナーや対応が必要となるため、戸惑う方も少なくありません。
ここでは、家族葬の香典返しに関する基本的な考え方から、お返しの時期、品物の相場、挨拶状の文例、のしの書き方、よくある質問まで、網羅的に解説します。
適切なマナーで感謝の気持ちを伝えられるよう、ぜひ参考にしてください。
そもそも家族葬で香典返しは必要?基本的な考え方
家族葬の場合でも、香典を受け取ったら香典返しは必要です。
家族葬は、参列者の金銭的負担を軽減したいという理由から、香典を辞退するケースも多いのですが、香典返しはいただいたご厚志に対するお返しであるため、葬儀の規模に関わらず、香典を受け取った場合にはお返しを贈るのが基本的なマナーとされています。
ただし、香典を辞退している旨を伝えても、弔問客が香典を持参する場合もあるため、その際は受け取って後日、家族葬の香典返しを用意しましょう。
家族葬では香典を辞退するケースが多い
家族葬は、従来の一般葬と比較して、香典を辞退するケースが多く見られます。これは、故人や遺族が参列者に金銭的な負担をかけたくないという配慮や、香典返しの準備にかかる手間を軽減したいという意向があるためです。
また、費用が抑えられる家族葬では、香典の必要性が低いと考える喪主もいます。そのため、あらかじめ案内状に香典を辞退する旨を明記することが一般的です。
しかし、香典辞退の意向を伝えても、弔意から香典を持参する方もいらっしゃるため、その場合は無理に受け取らないのではなく、感謝の気持ちを込めて受け取り、後日改めて家族葬の香典返しを用意することが大切です。
香典をいただいたらお返しをするのがマナー
家族葬であっても、香典をいただいた際にはお返しをするのが基本的なマナーです。
香典は、故人への弔意や遺族への支援の気持ちを表すものです。
そのため、香典を受け取った場合は、その気持ちに応える形で香典返しを贈ることが大切になります。
特に、親族や故人と親交の深かった方々から香典をいただいた場合は、感謝の気持ちを伝える意味でもお返しは欠かせません。
たとえ香典辞退の意向を伝えていても、相手の厚意を受け入れた際は、後日改めてお礼の品を贈るようにしましょう。
家族葬の香典返しは、故人や遺族への気遣いを示す大切な行為です。
香典返しが必要となる具体的な3つの場面
家族葬では香典を辞退するケースも多いですが、香典を受け取った場合は香典返しが必要です。
特に、葬儀の当日、現金書留などで郵送されてきた場合、後日の弔問の際に香典を受け取った場合の3つの場面では、適切な香典返しが必要となります。
それぞれの状況に応じた対応を把握し、失礼のないよう感謝の気持ちを伝えましょう。
葬儀当日に参列者から香典をいただいた場合
家族葬の当日、参列された親族や友人から香典をいただいた場合、香典返しが必要です。
近年では、葬儀当日に香典返しを渡す「当日返し(即日返し)」が一般的になっています。
これは、後日改めて香典返しを郵送する手間を省くことができるため、遺族の負担を軽減するメリットがあります。
当日返しの場合、香典の金額に関わらず、一律で2,000円から3,000円程度の品物を用意しておくのが一般的です。
ただし、高額な香典をいただいたことが後から判明した場合は、当日返しに加えて、後日改めて追加のお返しを贈ることがマナーとされています。
会葬御礼は香典の有無にかかわらず参列者全員に渡すものなので、香典返しとは別物として認識しておきましょう。
現金書留などで香典が郵送されてきた場合
家族葬に参列できなかった方から、現金書留などで香典が郵送されてくることがあります。この場合も、香典返しは必要です。
郵送で香典をいただいた場合は、まず電話で香典が届いたことへの感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。その後、忌明けの時期に合わせて、香典返しを郵送するのが一般的です。
品物を選ぶ際には、後述する香典返しの相場を参考に、いただいた金額の3分の1から半額程度の品物を選ぶようにします。
香典返しには、無事に葬儀を終えたことや、故人への生前の厚誼に対する感謝を伝える挨拶状を添えることがマナーです。
後日の弔問で香典を受け取った場合
葬儀後に、親族や故人の友人などが弔問に訪れ、香典をいただくケースもあります。たとえ事前に香典を辞退する旨を伝えていたとしても、相手の弔意を尊重し、香典は快く受け取るのがマナーです。
この場合、香典返しは、弔問を受けた日から1週間から10日以内に贈るのが望ましいとされています。忌明け後であれば、四十九日を過ぎてからでも問題ありません。
ただし、郵送で送る際には、品物とともに挨拶状を添え、後日になってしまったお詫びと、香典へのお礼を丁寧に伝えることが大切です。
特に、遠方から弔問に来られた方には、郵送の配慮が喜ばれるでしょう。
香典返しはいつ渡す?2つのタイミングと宗教別の時期
香典返しを渡すタイミングには、大きく分けて「当日返し」と「後日返し」の2種類があります。
また、宗教によって忌明けの時期が異なるため、それぞれに合わせた適切な時期を選ぶことが重要です。
感謝の気持ちを伝えるためにも、これらのタイミングとマナーを理解しておきましょう。
当日にお渡しする「即日返し」のメリット
「即日返し」とは、葬儀の当日に香典をいただいた方へ、その場で香典返しを渡す方法です。
この方法の最大のメリットは、遺族が後日改めて香典返しを手配する手間を大幅に軽減できる点にあります。
特に、一般葬のように参列者が多い場合や、遠方の親族や友人が多く、個別に郵送する手配が難しい場合に有効です。
当日返しでは、香典の金額に関わらず、一律で2,000円から3,000円程度の品物を用意するのが一般的です。
ただし、高額な香典をいただいた場合は、後日追加で香典返しを贈ることで、より丁寧な対応となります。
即日返しは、遺族の負担を減らしつつ、迅速に感謝の気持ちを伝えられる合理的な方法と言えるでしょう。
忌明け後にお渡しする「後日返し」の時期
香典返しのもう一つのタイミングは、「後日返し」として忌明け後に贈る方法です。
仏式では四十九日法要を終えた忌明け後1ヶ月以内、神式では五十日祭後1ヶ月以内、キリスト教では命日から1ヶ月後の追悼ミサまたは召天記念日を目安に贈ります。
この時期に香典返しを贈ることは、無事に忌明けを迎えられたことを報告する意味合いも持ちます。
後日返しは、香典の金額に合わせて品物を選べるため、いただいたご厚志にきめ細かく対応できる点がメリットです。
特に家族葬では、親族から高額な香典をいただくケースも多く、金額に応じて品物を選びたい場合に適しています。
郵送する際は、品物に挨拶状を添え、感謝の気持ちを伝えましょう。
香典返しの金額はいくらが適切?相場を解説
香典返しの金額は、いただいた香典の金額によって異なります。一般的な相場は「半返し」とされていますが、高額な香典をいただいた場合や会社からの香典など、状況に応じた柔軟な対応が必要です。適切な金額を知り、失礼のないよう感謝の気持ちを伝えましょう。
基本はいただいた金額の「半返し~3分の1」が目安
香典返しは、いただいた香典の金額に対して「半返し」、つまり半額程度の品物を贈るのが一般的な目安とされています。
例えば、1万円の香典をいただいた場合は、5,000円程度の品物をお返しします。
しかし、家族葬の場合は、親族など故人と近しい関係の方から高額な香典をいただくケースも多いため、必ずしも半返しにこだわる必要はなく、3分の1から4分の1程度の金額でも失礼にはあたりません。
遺族の経済的な負担を考慮し、無理のない範囲で感謝の気持ちを伝えることが大切です。
ただし、地域や親戚間での慣習がある場合は、そちらを優先することも検討しましょう。
高額な香典をいただいた場合の金額の決め方
高額な香典をいただいた場合、必ずしも半返しにこだわる必要はありません。
特に、3万円以上の高額な香典に対しては、3分の1から4分の1程度のお返しが目安とされています。
これは、高額な香典には遺族への経済的な援助や深い思いが込められていることが多く、無理に高額な香典返しをすることでかえって相手に気を遣わせてしまう可能性があるためです。
例えば、10万円の香典をいただいた場合は、3万円から5万円程度の品物をお返しするのが一般的です。
当日返しで一律の品物を渡している場合は、忌明け後に改めて追加のお返しを贈るようにしましょう。
この際、感謝の気持ちを伝えるお礼状を添えると、より丁寧な印象を与えます。
会社名義など連名でいただいた場合の対応
会社名義で香典をいただいた場合、原則として香典返しは不要です。
何かの機会に会った際に口頭でお礼を伝える程度で十分とされています。
ただし、会社の方々が連名で香典をくださった場合は、状況に応じて対応を検討しましょう。
少額の香典を連名でいただいた場合は、個別にお返しをするのではなく、お茶菓子などを職場に持参して皆で分けられるようにすると良いでしょう。
もし香典の金額が比較的多い場合は、金額を人数で割って一人当たりの金額を算出し、それぞれに見合った香典返しを贈ることもあります。
この際、個人名義で香典をくださった方には、別途香典返しを用意することがマナーです。
【目的別】家族葬の香典返しにおすすめの品物
家族葬の香典返しでは、どのような品物を選ぶべきか悩む方も多いでしょう。
ここでは、香典返しの定番である「消えもの」と呼ばれる品物や、相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフト、そして避けるべき品物とその理由について解説します。
感謝の気持ちを込めて、相手に喜ばれる品物を選びましょう。
お茶やお菓子など定番の「消えもの」ギフト
香典返しには、「不祝儀を後に残さない」という考え方から、消費するとなくなる「消えもの」と呼ばれる品物が適しています。
具体的には、お茶やコーヒー、海苔、お菓子などの食品や、石鹸、洗剤、タオルなどの日用品が定番です。
これらの品物は、好みが分かれにくく、どなたにでも喜ばれやすいため、安心して贈ることができます。
特にお茶は、故人を偲びながらゆっくりと過ごす時間を提供できることから、香典返しの品物として古くから選ばれています。
また、個包装のお菓子などは、ご家族で分けやすく、日持ちするものを選ぶとさらに喜ばれるでしょう。
相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフト
近年、香典返しの品物として人気が高まっているのがカタログギフトです。
カタログギフトの最大のメリットは、贈られた相手が自分の好みや必要なものを選べる点にあります。
家族構成や生活スタイルが多様化する中で、相手に本当に喜ばれる品物を贈るのは難しいこともありますが、カタログギフトであればそのような心配がありません。
食品や日用品はもちろん、ブランド品や体験型ギフトなど、幅広いジャンルの商品から選ぶことができるため、年代を問わず多くの方に喜ばれています。
特に、遠方に住む親族や友人への香典返しとして郵送する場合にも、かさばらず便利です。
香典返しとして避けるべき品物とその理由
香典返しの品物には、いくつかの避けるべきタブーがあります。
まず、肉や魚などの「四つ足生臭もの」と呼ばれる生鮮食品は、殺生を連想させるため、弔事には不適切とされています。
同様に、お酒などの嗜好品も、慶事に用いられることが多いため避けるべきです。
また、結婚式の引き出物で定番の鰹節や昆布も、「慶事を連想させる」という理由から香典返しにはふさわしくありません。
商品券や金券は、金額が露骨に分かってしまうため、しきたりを重んじる方からは不適切と捉えられる場合があります。
さらに、華やかなデザインや派手な包装の品物も、弔事の趣旨にそぐわないため控えるのがマナーです。
失敗しないための香典返しのマナー
香典返しを贈る際には、品物選びだけでなく、のし(掛け紙)の種類や表書きの書き方、そして感謝の気持ちを伝える挨拶状の有無など、さまざまなマナーが存在します。
特に家族葬の場合でも、これらのマナーは一般葬と変わらないため、しっかりと理解しておくことが大切です。
ここでは、失敗しないための香典返しの基本マナーについて解説します。
掛け紙(のし)の種類と正しい水引の選び方
香典返しには、一般的に「のし」ではなく「掛け紙」を使用します。慶事で使われる「のし」は、不祝儀には適さないため注意が必要です。
掛け紙に用いられる水引は、一度きりの弔事であることを表す「結び切り」を選びます。色は黒白または双銀が一般的ですが、関西から西日本では黄白の水引が使われる地域もあります。水引の本数は5本か7本がより一般的で求めやすいとされています。
表書きは、水引の上に書くもので、宗教や宗派によって異なりますが、一般的には「志」が無難です。水引の下には、喪主の氏名または「○○家」と記載します。
表書きの正しい書き方を宗教・宗派別に解説
香典返しの表書きは、宗教・宗派によって書き方が異なります。
仏式では、一般的に「志」または「満中陰志」と記載します。「満中陰志」は、関西地方でよく用いられる表現で、四十九日の忌明けを迎えたことへの感謝を示す意味があります。
神式の場合は、「志」または「偲び草(しのびぐさ)」と書くのが一般的です。
キリスト教では、香典返しの習慣自体が元々ありませんが、返礼品を贈る場合は「記念品」や「志」と記載します。
どの宗教・宗派でも、「志」は広く使われる表書きなので迷った際は「志」を選ぶと良いでしょう。
また、水引の下には喪家の姓、または喪主の氏名をフルネームで記入するのがマナーです。
感謝の気持ちを伝える挨拶状の書き方と文例
香典返しを郵送する際は、感謝の気持ちを伝える挨拶状を添えるのがマナーです。
家族葬の場合でも、挨拶状は故人を悼んでくださった方々への誠意と礼節を示す大切な手段となります。
挨拶状には、香典をいただいたことへの感謝、無事に四十九日法要を終えたことの報告、故人への生前の厚誼へのお礼、そして返礼品を贈る旨を記載するのが一般的です。
句読点を使用せず、重ね言葉や忌み言葉を避けるのが基本です。
以下に仏式の文例を示します。
拝啓
この度は亡き父○○の葬儀に際しまして、ご多忙の中ご会葬賜り、またご丁重なご厚志をいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、四十九日の法要も滞りなく済ませることができました。
つきましては供養のしるしとしまして、心ばかりの品をお贈りいたしましたので、何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます。
略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。
敬具
令和○年○月○日
喪主〇〇〇〇
キリスト教や神式の場合も、それぞれの宗教に合わせた用語を使用しましょう。
家族葬の香典返しでよくある質問
家族葬における香典返しに関して、よく寄せられる質問をまとめました。
「香典返しは不要」と伝えられた場合の対応や、忌明けを過ぎてしまった際のお返しの方法など、具体的な疑問を解決し、安心して対応できるよう解説します。
「香典返しは不要」と伝えられたらどうする?
「香典返しは不要です」と明確に伝えられた場合、または香典袋に「香典返し不要」の旨が記されている場合は、基本的に香典返しをする必要はありません。
相手の意向を尊重し、無理にお返しを贈ることでかえって気を遣わせてしまう可能性があるためです。
ただし、お礼の気持ちを伝えるために、忌明け後に改めてお礼状(礼状)を送ることがマナーとされています。
お礼状には、香典へのお礼と、香典返しを辞退されたことへの感謝の気持ちを記しましょう。
また、香典返しは受け取らないが、寄付をしてほしいという意向の場合もあります。
その際は、寄付をした旨を記載した挨拶状を送り、寄付先の情報も添えるとより丁寧です。
忌明けを過ぎてしまった場合のお返しの方法
香典返しは、仏式では四十九日法要の忌明け後1ヶ月以内を目安に贈るのが一般的ですが、何らかの事情で時期を過ぎてしまうこともあるでしょう。
忌明けを過ぎてしまった場合でも、香典返しは必ず贈るようにしましょう。時期が遅くなったからといってお返しをしないのは失礼にあたります。
遅れてしまった場合は、できるだけ早く香典返しを用意し、品物とともに、遅れたことへのお詫びと香典へのお礼を丁寧に記した挨拶状を添えて郵送します。お詫びの言葉を入れることで、相手に誠意が伝わり、理解を得やすくなるでしょう。
遅くなっても、感謝の気持ちを伝えることが最も大切です。
家族葬においても、香典を受け取った場合には香典返しが必要です。
香典返しは、いただいたご厚志への感謝と、無事に葬儀を終えたことを報告する意味合いを持ちます。
お返しの時期は、葬儀当日の「即日返し」と、忌明け後に行う「後日返し」の2つのタイミングがあり、宗教によって忌明けの時期が異なるため注意が必要です。
金額の相場は、いただいた香典の半額から3分の1程度が目安ですが、高額な香典や会社名義での香典には柔軟な対応が求められます。
品物としては、お茶やお菓子などの「消えもの」や、相手が自由に選べるカタログギフトがおすすめです。
のしや挨拶状の書き方にもマナーがあるため、適切な形式で感謝の気持ちを伝えましょう。
香典返しが不要と伝えられた場合や、忌明けを過ぎてしまった場合でも、お礼状などで丁寧に対応することが大切です。