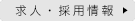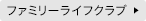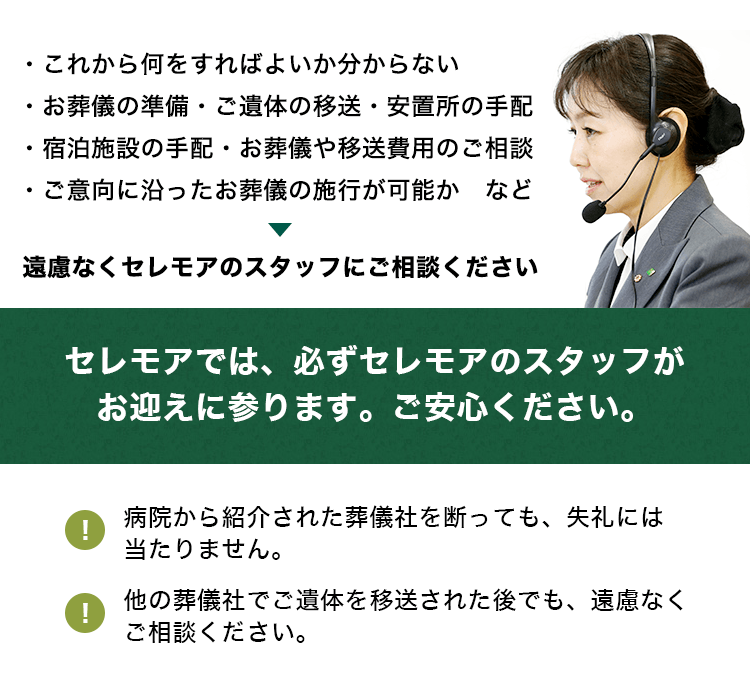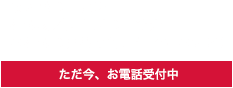家族葬の通夜の流れとは?服装・マナーから喪主の挨拶まで解説
最終更新:2025-08-30
家族葬は近年選ばれることの増えた葬儀形式で、故人のご遺族やごく親しい友人・知人のみが参列します。
一般葬と比較して小規模で行われるため、「お通夜は必要なのだろうか」「どのような服装で参列すれば良いのだろうか」など、疑問に感じる方も少なくありません。
家族葬のお通夜は、一般葬と同様に行われる場合もあれば、省略される場合もあります。
本記事では、家族葬におけるお通夜の一般的な流れ、適切な服装、守るべきマナー、そして喪主による挨拶のタイミングと内容について詳しく解説します。
そもそも家族葬で通夜は行うの?
家族葬においてお通夜を行うかどうかは、ご遺族の意向や故人の遺志によってさまざまです。
お通夜は、親しい方々が集まり故人との別れを惜しむ儀式であり、一般的に故人が亡くなった日の夜に行われます。
しかし、近年ではお通夜を行わない家族葬も増えており、告別式から火葬までを一日で行う「一日葬」や、儀式を省略し火葬のみを行う「火葬式(直葬)」といった形式も選ばれるようになりました。
お通夜をしないことで、ご遺族の精神的・体力的な負担を軽減できるというメリットもあります。
ただし、お通夜を省略する場合は、菩提寺や親族に事前に相談し、了承を得ておくことが大切です。施設によっては、お通夜を執り行わない形式に対応していない場合もあるため、事前に確認が必要でしょう。
【当日の流れ】家族葬における通夜の進行手順と所要時間
家族葬の通夜の進行手順は、基本的に一般葬と大きな違いはありません。
全体の流れを事前に把握しておくことで、落ち着いて当日を迎えられるでしょう。
通夜の開式から閉式までの所要時間は約1時間程度が一般的で、その後行われる通夜振る舞いを含めると、全体で約3時間程度を要するとされています。
喪主やご遺族は、通夜が始まる1時間ほど前には会場に到着し、葬儀社との最終確認や準備を行うことが推奨されます。
1. 受付開始:参列者を迎える
通夜の開始時刻の約30分~1時間前には、受付が開始されます。
喪主やご遺族は、その前に会場に到着し、返礼品や供花の配置などを最終確認します。
受付では、弔問に訪れた参列者から香典を受け取り、芳名帳への記帳をお願いするのが一般的な流れです。
家族葬の場合、参列者が少ない場合は受付を設けないこともありますが、設ける場合は、香典を辞退する旨を事前に受付係に伝えておく必要があります。
2. 僧侶入場と開式:通夜の始まり
通夜の開式時刻が近づくと、葬儀社の担当者から着席のアナウンスがあります。
参列者が着席した後、僧侶が入場し、通夜式が始まります。
僧侶の入場時には、地域や宗派、葬儀社の方針によって、一同起立して迎える、遺族だけが起立する、一同合掌で迎えるなど、様々な慣習があります。
司会者の案内に従い、故人を敬う気持ちを持って迎えましょう。
開式後は、読経が始まります。
3. 読経と焼香:故人を偲び冥福を祈る
僧侶による読経が始まると、続いて焼香が行われます。
まず僧侶が焼香を行い、その後、喪主、ご遺族、親族、そして一般の参列者の順に焼香を行います。
焼香の順番は血縁の濃い順が基本ですが、葬儀社の係員が案内してくれるため、指示に従いましょう。
焼香中は数珠を左手に持ち、心を込めて故人の冥福を祈ります。
焼香が終わると、僧侶による法話が行われる場合もあります。
この一連の流れがお通夜の中心的な儀式となります。
4. 僧侶退場と閉式:喪主が挨拶を行う
参列者全員の焼香が終わり、僧侶による法話が済むと、僧侶が退場し、通夜式は閉式となります。
僧侶が退場した後、喪主から参列者へ向けて挨拶を行います。
この挨拶では、参列いただいたことへの感謝、故人への生前の厚誼に対するお礼、そして通夜振る舞いへの案内などを簡潔に述べることが一般的です。
親しい間柄のみで行われる家族葬では、かしこまった表現でなくても問題ないとされています。
5. 通夜振る舞い:参列者をもてなす食事の席
通夜式が終了した後、故人の供養と参列者へのお礼のために、通夜振る舞いと呼ばれる食事の席が設けられます。
通夜振る舞いへの参加は必須ではありませんが、故人への供養となり、ご遺族を慰める意味合いもあるため、時間の許す限り立ち寄ることがマナーとされています。
ただし、ご遺族への負担を考慮し、長居はせず30分から1時間程度で引き上げるのが目安です。
家族葬では、この通夜振る舞いを「なし」にするケースや、簡単に済ませるケースも増えています。
【主催者向け】家族葬の通夜で喪主が気をつけるべきこと
家族葬の通夜で喪主が気を付けるべきことは多岐にわたります。
まず、通夜の進行だけでなく、参列者への配慮が非常に重要です。
特に挨拶の際には、参列してくれたことへの感謝の気持ちを伝えることを忘れてはなりません。
香典や供花を辞退する場合の明確な伝え方、参列者以外の関係者への訃報の連絡タイミングなども、事前に検討しておくべき点です。
参列をお願いする方への連絡方法
家族葬では、参列者を限定することが一般的です。
そのため、事前に参列をお願いする方々へは、明確にその旨を伝える必要があります。
訃報の連絡と同時に、家族葬であること、そして参列の範囲について具体的に伝えましょう。
これにより、参列を希望する方が迷うことなく、適切な行動をとることができます。
電話や案内状で丁寧に伝えることが大切です。
香典や供花を辞退する場合の伝え方
家族葬では、香典や供花、供物を辞退するケースが多く見られます。
香典を辞退する場合は、訃報の連絡時や案内状にその旨を明記しましょう。
例えば、「故人の遺志により、ご香典ご供花は固くご辞退申し上げます」といった文言を添えます。
受付を設ける場合は、受付係にも香典辞退の旨を伝えておく必要があります。
参列者が香典を持参した場合でも、無理に受け取らず、丁重にお断りすることが大切です。
参列者以外の方へ訃報を知らせるタイミング
家族葬では、ご遺族や親しい関係者のみで葬儀を執り行うため、それ以外の方には訃報を知らせるタイミングが重要になります。
一般的には、葬儀が滞りなく終了した後に訃報を伝えることが多いですが、故人の会社関係者やご友人など、生前特にお世話になった方々には、事前に家族葬である旨を伝えた上で、事後の連絡となることを理解してもらうのが望ましいでしょう。
訃報を受ける側の気持ちを考慮し、丁寧な対応を心がけることが大切です。
【参列者向け】家族葬の通夜に参列する際の基本マナー
家族葬の通夜に参列する際は、ご遺族の意向を尊重することが最も大切なマナーです。
一般的な葬儀とは異なり、参列者が限定されるため、まずは参列しても良いかどうかの確認が必要です。
香典を持参する際の注意点も把握しておきましょう。
基本的なマナーを守り、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが求められます。
お通夜に参列しても良いか遺族に確認する
家族葬の場合、ご遺族から案内があった場合のみ参列するのがマナーです。
訃報を受けた際に「家族葬で執り行います」という連絡があった場合は、原則として参列は控えるのが一般的です。
もし参列を希望する場合は、必ず事前にご遺族に連絡を取り、参列しても良いか確認しましょう。
ご遺族は、弔問を断りにくいと感じることもあるため、配慮が必要です。
無理に参列しようとせず、ご遺族の意向を尊重することが大切になります。
香典を持参するときの注意点
家族葬では香典を辞退するケースが多いため、香典を持参する際は注意が必要です。
ご遺族から明確に香典辞退の連絡があった場合は、香典を持参する必要はありません。その意向を尊重し、無理に渡そうとせず持ち帰りましょう。
もし香典辞退の連絡が特にない場合は、一般的な相場に合わせて香典を持参するのが良いとされています。
しかし、当日受付で改めて香典辞退の案内を受ける可能性もあるため、その際も丁重に従うようにしましょう。
家族葬の通夜にふさわしい服装を立場別に解説
家族葬の通夜に参列する際の服装は、立場によって多少の違いはあるものの、基本的には一般的なお通夜と同じく準喪服を着用することが一般的です。
故人を偲び、ご遺族への敬意を表すために、派手すぎず、落ち着いた服装を心がけることが重要です。
ここでは、男性、女性、子どもの服装について、それぞれ詳しく解説します。
男性の服装:準喪服を着用する
男性の服装は、準喪服であるブラックスーツが基本です。
光沢のない黒のスーツを選び、中に白い無地のワイシャツを着用します。
ネクタイは黒無地、または織り柄入りの黒を選びましょう。
靴下と靴も黒で統一し、ネクタイピンやアクセサリーはつけません。
急な訃報で通夜に駆けつける場合は、略喪服としてダークカラーのスーツ(濃紺やダークグレーなど)でも問題ないとされる場合もありますが、葬儀・告別式には準喪服が望ましいです。
清潔感があり、故人への敬意を示す服装を心がけましょう。
女性の服装:準喪服を着用しアクセサリーに注意する
女性の服装も、準喪服であるブラックフォーマルが基本です。
黒のワンピースやアンサンブル、スーツ、またはパンツスーツを選びましょう。
いずれも光沢感や装飾のない無地の黒が適切です。
アクセサリーは、結婚指輪以外は基本的には避けますが、真珠の一連ネックレスや一粒イヤリング・ピアスは着用しても問題ありません。
ただし、二連以上のネックレスや、派手なデザインのものは避けましょう。
靴やバッグも黒で統一し、光沢のある素材は避けるのがマナーです。
通夜に駆けつける際は略喪服でもよいとされていますが、葬儀・告別式は準喪服が適しています。
子どもの服装:制服または暗い色の私服を選ぶ
子どもの服装は、学校の制服がある場合は制服を着用するのが最も適切です。
制服がない場合は、黒、紺、グレーなどの暗い色の地味な服装を選びましょう。
キャラクターがプリントされた服や派手な色合いの服は避けます。
靴も落ち着いた色を選び、清潔感を保つことが大切です。
特に乳幼児の場合は、無理にフォーマルな服装にこだわる必要はなく、派手でない普段着で構いません。
【例文付き】喪主が行う挨拶のタイミングと内容
家族葬においても、喪主による挨拶は重要な役割を果たします。
参列してくださった方々への感謝の気持ちを伝える機会であり、故人を見送る上で欠かせません。
喪主の挨拶は、主に通夜閉式の際、通夜振る舞いの開始時、そして通夜振る舞い終了時の3つのタイミングで行われることが多いです。
ここでは、それぞれのタイミングに応じた挨拶の例文と、押さえておくべき内容について解説します。
通夜閉式の挨拶
通夜閉式の挨拶は、通夜の儀式が全て滞りなく終了したことを参列者に報告し、故人への弔意と参列への感謝を伝える場です。
一般的に、僧侶が退場した後に行われます。
親しい身内のみの家族葬であれば、かしこまりすぎず、心からの感謝を伝えることが大切です。
(例文)
本日はお忙しい中、亡き〇〇(故人の名前)の通夜にご参列いただき、誠にありがとうございました。
故人も皆様にお見送りいただき、さぞ喜んでいることと存じます。
つきましては、ささやかではございますが、別室にてお食事の席をご用意いたしました。
故人の思い出話などをお聞かせいただければ幸いです。
本日は誠にありがとうございました。
通夜振る舞いを開始する際の挨拶
通夜振る舞いを開始する際の挨拶は、参列者への感謝と共に、食事の席へと案内する役割があります。堅苦しくなりすぎず、和やかな雰囲気で故人を偲ぶ時間となるよう促しましょう。
「皆様、本日はご多用の中、故〇〇(故人の名前)のために、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。皆様に見守られ、故人も安堵していることと存じます。ささやかではございますが、故人を偲びながらお食事をお召し上がりいただければ幸いです。どうぞ、ゆっくりお過ごしください。」
通夜振る舞いを終了する際の挨拶
通夜振る舞いを終了する際の挨拶は、参列者へのねぎらいと感謝の気持ちを伝え、散会を促すものです。夜も更けてきたことへの配慮を示し、翌日の葬儀・告別式の案内を簡潔に加えることもあります。
「皆様、本日は誠にありがとうございました。故人の思い出話は尽きませんが、夜も更けてまいりましたので、この辺りでお開きとさせていただきます。お気をつけてお帰りください。なお、明日は午前〇時より、当斎場にて葬儀・告別式を執り行います。何卒よろしくお願い申し上げます。」
お通夜を省略する家族葬の形式
家族葬は、必ずしもお通夜を行うとは限りません。
近年では、ご遺族の負担軽減や費用を抑える目的から、お通夜を省略する形式の家族葬が増えています。
お通夜をしないことで、葬儀全体の流れが大きく変わるため、事前に把握しておくことが重要です。
ここでは、お通夜を省略する代表的な家族葬の形式である「一日葬」と「火葬式(直葬)」について解説します。
一日葬:告別式から火葬までを1日で行う形式
一日葬は、お通夜を行わず、葬儀・告別式から火葬までを1日で執り行う形式です。
これにより、2日間にわたる葬儀の精神的・体力的な負担を軽減できるという大きなメリットがあります。
また、葬儀費用を抑えることも可能です。
ただし、菩提寺や親族の中には、お通夜を省略することに抵抗がある方もいるため、事前にしっかり相談し、理解を得ておくことが大切です。
一日葬は、高齢の参列者が多い場合や、遠方からの参列者がいる場合にも選ばれています。
火葬式(直葬):儀式を省略し火葬のみを行う形式
火葬式、または直葬は、お通夜や告別式といった宗教的な儀式をほとんど行わず、火葬のみを執り行う最もシンプルな形式の家族葬です。
ご遺体をご安置した後、直接火葬場へ搬送し、火葬を行います。故人との最後のお別れは、火葬炉の前で数分間行われることが一般的です。
儀式を大幅に省略するため、費用を最も抑えられるのが特徴です。しかし、故人とゆっくりお別れをする時間が少ないため、後悔が残る可能性もあります。
また、菩提寺がある場合は、事前に相談して了承を得ておく必要があります。告別式なしの形式であるため、参列者が故人との別れを惜しむ機会が限られる点も考慮しておきましょう。
家族葬の通夜に関するよくある疑問
家族葬は比較的新しい葬儀の形式であるため、お通夜に関する疑問を抱く方も少なくありません。
ここでは、家族葬の通夜でよくある質問について解説します。
友人参列の可否、通夜振る舞いの必要性、弔問を希望する方への対応など、具体的な疑問を解消し、安心して故人を見送れるよう準備を進めましょう。
友人が通夜に参列することはできますか?
家族葬は、故人のご家族やご親族、生前特に親しかったご友人のみが参列することが一般的です。
そのため、ご友人が通夜に参列することは可能です。
ただし、ご遺族が参列者を限定している場合もあるため、訃報を受けた際に「家族葬で執り行います」という連絡があった場合は、まずはご遺族に連絡を取り、参列しても良いか確認することが大切です。
ご遺族の意向を尊重し、無理に参列を申し出ることは避けましょう。
通夜振る舞いは必ず行わなければいけませんか?
通夜振る舞いは、故人の供養と参列者への感謝を表すための食事の席ですが、必ずしも行わなければならないという決まりはありません。
家族葬においては、参列者の人数が少ないことや、ご遺族の負担軽減の観点から、通夜振る舞いを「なし」にするケースも増えています。
簡単な軽食を用意する、または飲食自体を省略するなど、ご遺族の意向や状況に合わせて柔軟に決めることができます。
ただし、もし通夜振る舞いを省略する場合は、事前に参列者にその旨を伝えておくと良いでしょう。
弔問を希望する方にはどのように対応すればよいですか?
家族葬では、参列者を限定しているため、葬儀に参列できなかった方から後日弔問を希望されることがあります。
このような場合、ご遺族は相手の気持ちを考慮し、丁寧に対応することが求められます。
弔問を受け入れる場合は、事前に日時を決め、場所も自宅か別の場所かを伝えます。
自宅で弔問を受ける場合は、無理のない範囲で準備を行いましょう。
香典や供花を辞退する意向であれば、その旨を改めて伝えることも大切です。
相手の状況も考慮し、柔軟に対応することが、トラブルを避けることにつながります。
家族葬におけるお通夜は、一般葬と同様に行われる場合もあれば、ご遺族の意向や故人の遺志により省略される場合もあります。
お通夜を行う場合の進行手順は、受付から読経・焼香、喪主の挨拶、通夜振る舞いへと進み、所要時間は儀式のみで約1時間、通夜振る舞いを含めると約3時間が目安です。
喪主は、参列者への連絡方法、香典や供花辞退の伝え方、そして挨拶の内容とタイミングに注意が必要です。
参列者は、ご遺族の意向を尊重し、事前に参列の可否を確認すること、香典を持参する際の注意点を守ることがマナーとなります。
服装は、喪主・参列者ともに準喪服が基本ですが、子どもの場合は制服や暗い色の私服で問題ありません。
お通夜を省略する形式として一日葬や火葬式(直葬)があり、それぞれメリットとデメリットがあります。
家族葬の通夜に関するよくある疑問として、友人の参列、通夜振る舞いの必要性、弔問への対応が挙げられます。
これらの情報を参考に、故人を偲び、ご遺族に寄り添った対応を心がけましょう。