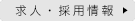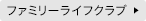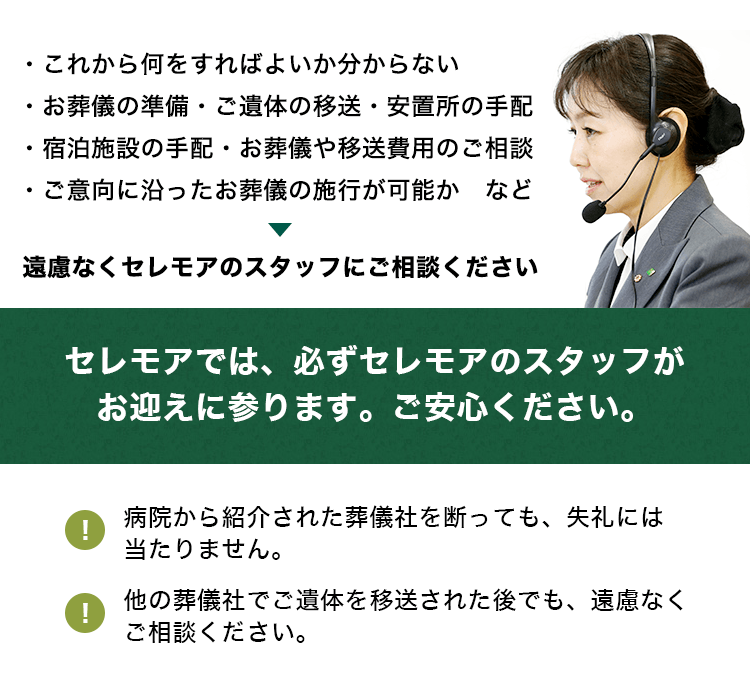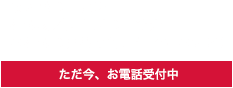一日葬儀とは?通夜なしの流れや費用、注意点をわかりやすく解説
最終更新:2025-09-30
一日葬とは、お通夜を行わずに告別式と火葬を一日で執り行う葬儀形式です。 遺族や参列者の心身的な負担を軽減でき、費用も抑えられる傾向にあるため、近年選択する方が増えています。
この記事では、一日葬の基本的な知識から具体的な流れ、費用の相場、メリット・デメリット、そして後悔しないための注意点までを網羅的に解説します。
通夜を行わない葬儀形式「一日葬」の基礎知識
一日葬は、宗教的な儀式である通夜を省略し、告別式から火葬、収骨までを一日で済ませる葬儀のスタイルを指します。
参列者の高齢化やライフスタイルの多様化を背景に、遺族や参列者の体力面や費用面の負担を軽くしたいというニーズから注目されるようになりました。
伝統的な形式を簡略化したものですが、故人を偲ぶ気持ちを大切にする点は他の葬儀と何ら変わりません。
一日葬と一般葬の大きな違い
一日葬と一般葬の最も大きな違いは、葬儀にかかる日数です。
一般葬では、1日目に通夜、2日目に告別式と火葬を執り行うため、儀式だけで2日間を要します。
ご逝去された日から数えると、3日以上かかることも珍しくありません。
一方、一日葬は通夜を行わないため、告別式と火葬を1日で完結させます。
この日程の短縮により、遺族や遠方からの参列者が拘束される時間が大幅に減り、宿泊などの負担も軽減されます。
ご逝去から2日目に告別式と火葬を行うケースが一般的です。
一日葬と家族葬の形式的な違い
一日葬と家族葬は混同されやすいですが、その定義は異なります。
一日葬が通夜の有無という「日程や流れ」に関する形式であるのに対し、家族葬は参列者を家族や親しい親族、友人に限定する「規模」に関する形式を指します。
したがって、参列者を限定して通夜を行わない「家族葬の一日葬」という形も存在します。
家族葬でも通夜と告別式を2日間にわたって行うのが基本ですが、一日葬と組み合わせることで、よりシンプルで身内だけのお別れが可能です。
両者はどちらかを選ぶものではなく、組み合わせられる概念だと理解しておきましょう。
ご逝去から火葬まで|一日葬の具体的な流れ
一日葬を選択した場合、ご逝去されてから火葬・収骨に至るまで、どのような流れで進むのでしょうか。
通夜がない点以外は、一般的な葬儀と共通する部分も多くあります。
ここでは、臨終のときから儀式が完了するまでの具体的な流れを3つのステップに分けて解説します。
事前に全体の流れを把握しておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。
ステップ1:ご逝去からご遺体の安置まで
医師による死亡確認後、まずご遺体を安置する場所へ搬送する必要があります。
法律により死後24時間は火葬ができないため、ご自宅か斎場の安置室などに最低1日ご遺体を安置します。
この点は一般葬と変わりません。
病院で亡くなられた場合は、速やかに葬儀社へ連絡し、寝台車でのお迎えを依頼します。
安置場所が決まったら、枕飾りを整え、菩提寺がある場合は連絡を入れます。
この安置期間中に、葬儀社と具体的な葬儀内容の打ち合わせを進めていくことになります。
ステップ2:葬儀社との打ち合わせと納棺
ご遺体の安置後、葬儀社の担当者と詳細な打ち合わせを行います。
この時に一日葬を希望する旨を明確に伝え、日程や式場、祭壇や棺の種類、返礼品などを決定していきます。
費用の見積もりもこの段階で詳細に確認し、プランに含まれる内容と追加で発生する費用をしっかり把握することが重要です。
打ち合わせを経て葬儀内容が固まったら、故人の旅支度を整え、ご遺体を棺に納める「納棺の儀」を執り行います。
この儀式は、家族が故人と触れ合える最後の機会となる大切な時間です。
ステップ3:告別式から火葬・収骨までの進行
葬儀当日は、告別式と火葬を同日中に行います。
一般的には午前中に斎場で告別式を開始し、僧侶による読経や弔辞の奉読、参列者による焼香などを進めます。
告別式の終了後、棺に花などを手向ける「お花入れの儀」で故人との最後のお別れをします。
その後、霊柩車で火葬場へ出棺し、火葬許可証を提出して火葬を行います。
火葬にかかる時間は1〜2時間程度で、その間は控室で待機します。
火葬が終わると、遺骨を骨壷に納める「収骨(お骨上げ)」を近親者で行い、一連の儀式は終了となります。
一日葬にかかる費用の相場と詳しい内訳
一日葬は通夜を行わない分、一般葬に比べて費用を抑えられる傾向にあります。
しかし、具体的にどのような項目にどれくらいの費用がかかるのか、内訳を把握しておくことが大切です。
葬儀全体の費用は、主に「葬儀一式費用」「宗教者へのお礼」「別途必要な費用」の3つに大別されます。
それぞれの相場と内容を理解し、予算を立てる際の参考にしてください。
葬儀一式にかかる費用の目安
葬儀一式費用は、葬儀を執り行うために最低限必要となるサービスや物品の料金で、葬儀社が提示するプランに含まれることがほとんどです。
具体的には、ご遺体の搬送・安置費用、棺や骨壷、祭壇の費用、式場の設営・運営に関わる人件費などが該当します。
一日葬のプラン料金の相場は、30万円から50万円程度が目安となります。
ただし、プランによって含まれる内容が異なるため、祭壇のグレードや棺の種類などを変更すると追加料金が発生する場合もあります。
契約前に内容を細かく確認することが不可欠です。
お布施など宗教者へのお礼の相場
仏式の葬儀で僧侶に読経などを依頼する場合、お礼としてお布施をお渡しします。
一日葬では通夜の読経がないため、2日間の儀式を依頼する一般葬よりもお布施の額は少なくなる傾向にあります。
一日葬でのお布施の相場は、10万円から20万円程度が目安とされていますが、寺院との関係性や宗派、地域によって変動します。
また、お布施とは別に、僧侶の交通費として「御車代」や、会食に参加されない場合の「御膳料」をそれぞれ5千円から1万円程度包むこともあります。
金額に迷う場合は、葬儀社や寺院に直接尋ねても失礼にはあたりません。
火葬料金や飲食費など別途必要な費用
葬儀社のプラン料金以外にも別途必要となる費用があります。
代表的なものは火葬場の使用料、参列者をもてなす飲食費、会葬返礼品代などです。
火葬料金は公営か民営か、またお住まいの地域によって大きく異なり、数万円から十数万円と幅があります。
飲食費は告別式後の会食(精進落とし)を行う場合に発生します。
返礼品は参列者の人数に応じて費用が変わります。
これらの費用は葬儀の規模や内容によって変動するため、総額がいくらになるのか事前に葬儀社としっかり確認しておく必要があります。
一日葬を選ぶことで得られる3つのメリット
一日葬が選ばれる背景には、現代社会のニーズに合った多くのメリットが存在します。
特に、時間的・体力的・経済的な負担を軽減できる点が大きな魅力とされています。
葬儀形式を検討する上で、これらのメリットが自分たちの状況や希望に合っているかを確認することは非常に重要です。
ここでは、一日葬を選ぶことで得られる代表的な3つのメリットについて詳しく見ていきます。
遺族の心身的な負担が軽減される
一般葬では通夜と告別式が2日間にわたるため、遺族は弔問客への挨拶や通夜振る舞いの対応などに追われ、心身ともに大きな負担がかかります。
特に高齢の遺族にとっては、長時間の儀式は体力的に厳しいものです。
一日葬では、儀式が1日で終了するため拘束時間が短縮され、体力的な消耗を抑えることが可能です。
故人を亡くした悲しみの中で、葬儀の対応に追われる精神的な負担も、通夜がなくなることで幾分か軽減されるという側面があります。
遠方からの参列者の負担も軽くなる
親族や友人が遠方に住んでいる場合、一般葬に参列するためには宿泊を伴うケースが多くなります。
これには宿泊費や交通費といった金銭的な負担に加え、仕事を休むなどの時間的な調整も必要です。
一日葬であれば、儀式が日中に終わるため、遠方からでも日帰りで参列できる可能性が高まります。
これにより、参列者の経済的・時間的な負担を大幅に減らすことができ、結果として「参列したかったけれど、都合がつかなかった」という人を減らすことにもつながります。
通夜を行わないため費用を抑えやすい
経済的なメリットも一日葬の大きな特徴です。
通夜を行わないことで、まず通夜振る舞いにかかる飲食費が不要になります。
また、式場を2日間押さえる必要がなくなるため、会場使用料を1日分に抑えられる場合があります。
遠方から来る親族のために用意していた宿泊費なども削減できます。
これらの費用がなくなることで、葬儀全体の総額を一般葬に比べて低く抑えることが可能です。
葬儀費用をできるだけ簡素に、かつ丁寧に行いたいと考える方にとって、これは大きな利点となります。
一日葬を選ぶ前に知っておきたいデメリット
多くのメリットがある一日葬ですが、その一方でいくつかのデメリットや注意点も存在します。
負担軽減や費用の面だけを見て安易に決定してしまうと、後で「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。
ここでは、一日葬を選ぶ前に必ず理解しておくべきデメリットを3つ挙げ、それぞれの内容と対策について解説します。
これらを事前に把握し、慎重に検討することが大切です。
故人とゆっくりお別れする時間が短くなる
通夜は、親しい人々が集い、故人に寄り添いながら思い出を語り合う、大切なお別れの時間です。
一日葬ではこの通夜がないため、葬儀全体が慌ただしく感じられ、故人とゆっくり向き合う時間が十分に取れないと感じる方もいます。
また、告別式は平日の日中に行われることが多いため、仕事などの都合でどうしても参列できず、故人と最後のお別れをする機会を逃してしまう友人が出てくる可能性も考慮しなければなりません。
お別れの時間を何よりも重視したい場合には、慎重な検討が必要です。
菩提寺や一部の親族から理解を得られない場合がある
一日葬は比較的新しい葬儀形式であるため、伝統を重んじる親族や地域によっては、快く思われない可能性があります。
「通夜を行うのが当たり前」という考えを持つ方から、簡略化しすぎていると反対されるケースも考えられます。
特に注意が必要なのは、菩提寺(檀家となっているお寺)との関係です。
お寺によっては、通夜を行わない葬儀を正式なものと認めず、その後の納骨を受け入れてもらえないといったトラブルに発展することもあります。
必ず事前に相談し、了承を得ることが不可欠です。
葬儀後に自宅への弔問客が増える可能性がある
葬儀当日の対応負担は軽減されますが、その反動として葬儀後に自宅へ弔問に訪れる人が増える傾向があります。
告別式に参列できなかった友人や会社関係者などが、後日改めてお焼香をあげに訪れるケースです。
その都度、個別の対応が必要になるため、結果的に葬儀後も落ち着かない日々が続き、かえって遺族の負担が増えてしまうことも考えられます。
葬儀後の弔問がある程度続くことをあらかじめ想定し、家族間で対応について話し合っておくと良いでしょう。
後悔しない一日葬にするための注意点
一日葬を滞りなく、そして関係者全員が納得できる形で執り行うためには、事前の準備と周囲への配慮が欠かせません。
メリットとデメリットを十分に理解した上で、いくつかの重要なポイントを押さえておくことで、後々のトラブルを防ぎ、故人を心から見送ることができます。
ここでは、後悔のない一日葬にするために、特に気をつけるべき3つの注意点について解説します。
親族や菩提寺へ事前に相談し理解を得る
一日葬を検討する際、最も重要なのが関係者への事前相談です。
特に年配の親族や、菩提寺がある場合は必ず意向を確認しましょう。
なぜ一日葬を選びたいのか、故人の遺志や遺族の体力的な事情などを丁寧に説明し、理解を求める姿勢が大切です。
一方的に決定してしまうと、後々まで続く関係性の悪化につながりかねません。
菩提寺には、一日葬という形式で供養をお願いできるか、そしてその後の納骨に問題はないかを明確に確認し、許可を得てから葬儀社との打ち合わせを進めるようにしてください。
参列できない方への配慮を忘れない
一日葬は平日の日中に行われることが多いため、仕事の都合などで参列が難しい方が出てくることを念頭に置く必要があります。
葬儀の案内をする際には、一日葬であることを明確に伝え、参列が難しい場合はお気持ちだけで十分であることを書き添えるなど、相手を気遣う一言を加えると丁寧です。
また、葬儀を終えた後には、無事に式を執り行ったことを報告する挨拶状を送るなど、参列できなかった方へのフォローを忘れないようにします。
こうした配慮が、その後の良好な人間関係を維持することにつながります。
香典や供物を辞退する場合の伝え方を決めておく
家族葬と兼ねた小規模な一日葬では、参列者の負担を考慮して香典や供物を辞退するケースも少なくありません。
辞退を決めた場合は、その意向が明確に伝わるよう、案内状に「誠に勝手ながら故人の遺志により御香典御供物の儀は固くご辞退申し上げます」といった一文を記載します。
それでも当日持参された方への対応も、事前に家族や葬儀社と相談して決めておくとスムーズです。
感謝の気持ちを伝えた上でお断りするのか、一度お預かりして後日返礼品を送るのかなど、対応を統一しておくことが混乱を避けるポイントです。
一日葬に関するよくある質問
一日葬を検討するにあたり、具体的な流れや費用以外にも、服装のマナーや参列者の範囲など、細かな点で疑問が浮かぶこともあるかもしれません。
いざという時に慌てないためにも、事前に疑問を解消しておくことが大切です。
この章では、一日葬に関して特に多く寄せられる3つの質問を取り上げ、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
Q. 一日葬での服装のマナーは一般葬と同じですか?
一日葬であっても服装に関するマナーは一般葬と全く同じです。
通夜がないだけで、告別式は故人を見送るための正式な儀式であるため、マナーに沿った服装が求められます。
遺族や親族は正喪服、一般の参列者は準喪服を着用します。
男性はブラックスーツに白無地のワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴と靴下を着用し、女性は黒のワンピースやアンサンブル、スーツに黒のストッキングと布製のパンプスを合わせます。
光沢のある素材や華美なアクセサリーは避け、故人への弔意を示す装いを心がけてください。
Q. 参列者はどの範囲まで呼ぶのが一般的ですか?
一日葬でどこまでの範囲の方に参列をお願いするかに、明確な決まりはありません。
故人や遺族の意向によって、家族と近しい親族のみで執り行うこともあれば、故人と親交の深かった友人や知人まで声をかけるケースもあります。
ただし、通夜がなく弔問の機会が限られること、そして平日の日中に行われることが多いため、結果的に参列者は近親者に絞られる傾向にあります。
誰に声をかけるべきか迷った場合は、家族で話し合い、故人との関係性を考慮しながらお声がけするのが良いでしょう。
Q. 菩提寺がない場合でも一日葬はできますか?
はい、菩提寺がない場合でも一日葬を行うことは全く問題ありません。
菩提寺がないということは、特定の寺院の檀家ではないということなので、宗教的なしきたりに縛られることなく、比較的自由に葬儀の形式を選べます。
もちろん、仏式の儀式を希望する場合は、葬儀社に相談すれば希望の宗派の僧侶を紹介してもらうことが可能です。
また、特定の宗教によらない無宗教形式で、故人が好きだった音楽を流したり、思い出の写真を飾ったりするなど、自由な形でお別れの会を執り行うことも選択肢の一つとなります。
一日葬は、通夜を行わず告別式と火葬を1日で執り行う葬儀形式です。
遺族や参列者の心身的な負担や費用を軽減できるメリットがある一方、故人とゆっくりお別れする時間が短くなる、菩提寺や親族の理解が必要になるなどの側面も持ち合わせています。
後悔のない葬儀にするためには、これらの特徴を十分に理解した上で、関係者への事前の相談が不可欠です。
本記事で解説した流れや費用、注意点を参考に、故人と遺族にとって最もふさわしいお見送りの形を慎重に検討してください。