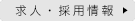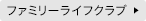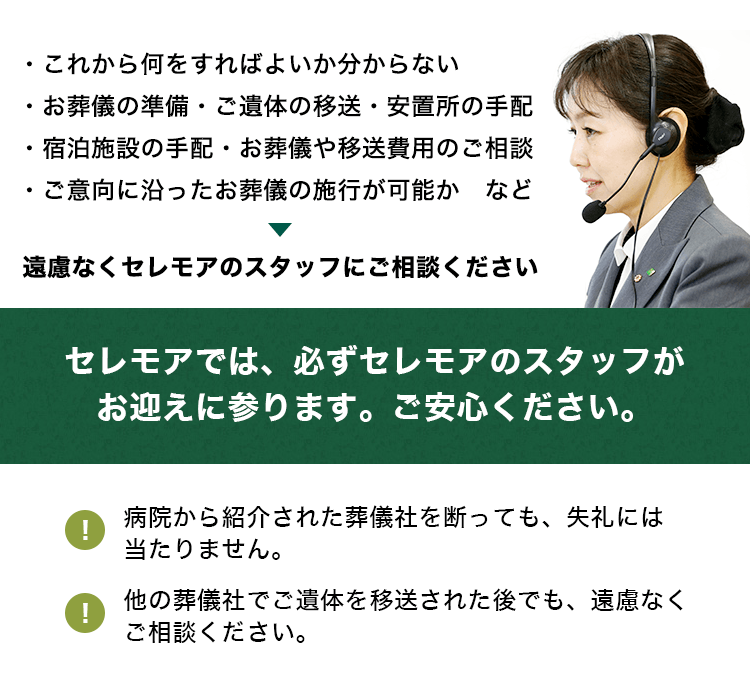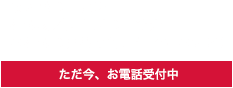一日葬の費用平均はいくら?相場や内訳、家族葬との違いを解説
最終更新:2025-09-30
身内のお葬式を考える際、多くの人が葬儀費用の負担に頭を悩ませます。
近年、費用を抑えつつ故人とのお別れを大切にできる葬儀形式として「一日葬」が注目されています。
この記事では、一日葬の全国的な費用平均やその内訳、一般葬や家族葬といった他の形式との違いを詳しく解説します。
自分たちの状況に最適な選択をするための情報として、ぜひ参考にしてください。
一日葬とは?通夜を行わない新しいお葬式の形
一日葬とは、お通夜を行わず、告別式から火葬までを1日で執り行うお葬式の形式です。
通常の二日間にわたるお葬式に比べて、遺族や参列者の身体的・経済的な負担を軽減できることから、近年その割合が増えています。
1日葬は、儀式を省略するわけではなく、お別れの時間を大切にしながらも、スケジュールをコンパクトにした現代のニーズに合ったスタイルと言えます。
費用を抑えたい、あるいは参列者の高齢化を考慮したいといった場合に選ばれることが多いです。
一日葬にかかる費用の全国的な平均相場
一日葬にかかる費用の全国的な平均相場は、40万円から60万円程度とされています。
ただし、この金額は参列者の人数や斎場の規模、祭壇のグレードなどによって変動します。
例えば、飲食費や返礼品が不要な、ごく少人数で行う場合は30万円程度に収まることもあります。
一方で、一般葬の平均費用が100万円以上であることを考えると、一日葬は通夜を行わない分、斎場利用料や飲食費などを大幅に抑えることが可能です。
具体的な費用を知るためには、葬儀社から詳細な見積もりを取ることが重要です。
【項目別】一日葬の費用内訳を詳しく解説
一日葬の総額費用は、複数の項目から構成されています。
大きく分けると、葬儀そのものに必要な「葬儀一式費用」、式場や火葬場を使用するための「施設利用料」、参列者をもてなすための「飲食費・返礼品費」、そして宗教者に支払う「お礼」の4つです。
これらの料金は、選択するプランや参列者の人数によって大きく変動します。
見積もりを確認する際は、どの項目にどれくらいの費用がかかっているのかを正確に把握し、自分たちの希望に合っているか検討することが大切です。
葬儀一式にかかる基本的な費用
葬儀一式費用は、お葬式を執り行うために最低限必要となるサービスや物品の費用をまとめたものです。
多くの場合、葬儀社が提示する基本プランに含まれています。
具体的な内容としては、ご遺体の搬送費用や安置施設利用料、ドライアイスなどの処置費用、棺や骨壺、遺影写真、祭壇の設営費用、そして当日の運営をサポートするスタッフの人件費などが挙げられます。
プランによって含まれる内容は異なるため、契約前には何が含まれていて、何がオプション(追加費用)になるのかを詳細に確認することが、後々のトラブルを避けるために不可欠です。
この葬儀の基本料金が全体の費用の大部分を占めます。
斎場や火葬場の施設利用料
一日葬を行うためには、告別式を執り行う斎場と火葬場の利用料が必要です。
斎場の利用料は、公営か民営かによって価格が大きく異なります。
自治体が運営する公営斎場は、比較的安価な料金設定になっており、故人や喪主がその地域の住民であればさらに割引が適用される場合もあります。
一方、民営斎場は設備が充実していることが多いですが、費用は高くなる傾向にあります。
また、火葬場の利用料も必要で、これも公営か民営かで差があります。
斎場と火葬場が併設されている施設を選ぶと、移動の手間や費用を省くことが可能です。
参列者に対するおもてなしの費用
参列者に対するおもてなしの費用は、主に火葬中や式後に提供される食事や飲み物代、香典返しとなる返礼品の費用を指します。
一日葬では通夜を行わないため、通夜振る舞いの費用はかかりません。
おもてなしの費用は、参列者の人数に比例して変動する代表的な項目です。
そのため、親族だけでなくどこまでの友人・知人に声をかけるかによって、総額が大きく変わります。
事前に参列者の範囲とおおよその人数を想定しておくことで、予算を立てやすくなります。
費用を抑えたい場合は、食事の形式を簡素にしたり、返礼品のグレードを見直したりするなどの工夫が考えられます。
宗教者へのお礼(お布施など)
仏式の葬儀で僧侶に読経や戒名の授与を依頼する場合、お礼としてお布施をお渡しします。
お布施はサービスの対価ではないため明確な金額は決まっていませんが、地域や宗派、寺院との関係性によってある程度の相場が存在します。
一日葬では通夜の読経がないため、二日葬に比べてお布施の金額が抑えられる傾向にあります。
一般的には、お布施の他に、僧侶が斎場まで足を運ぶための交通費として「御車代」や、会食に同席しない場合の食事代として「御膳料」を別途お渡しすることもあります。
金額に不安がある場合は、事前に葬儀社や寺院に相談してみるのがよいでしょう。
他の葬儀形式と一日葬の費用を比較
一日葬の費用を考える上で、他の葬儀形式との比較は欠かせません。
葬儀には、古くからの形式である「一般葬」、親しい人のみで送る「家族葬」、儀式を省略する「直葬」など、様々な選択肢があります。
一日葬は、これらの形式の中間に位置づけられることが多く、費用面でもその特徴が表れます。
それぞれの形式の内容と費用の違いを理解することで、故人や遺族の意向に最も合ったお別れの形を見つけることができます。
一般葬(二日葬)との費用差はどれくらい?
一般葬(二日葬)は、通夜と告別式の二日間にわたって行われる伝統的な葬儀形式です。
一日葬との最も大きな違いは通夜の有無であり、これが費用差に直結します。
一日葬では通夜を行わないため、通夜振る舞いの飲食費や、2日分の斎場使用料がかかりません。
また、遠方からの参列者の宿泊費といった付随的な負担も軽減されます。
一般葬の平均費用が100万円を超えることもあるのに対し、一日葬は40万円から60万円程度が相場であり、数十万円単位で費用を抑えることが可能です。
儀式の形を保ちつつ、経済的な負担を減らしたい場合に適した選択肢と言えます。
家族葬との費用や内容の違い
家族葬は、参列者を家族や親族、ごく親しい友人に限定して行う葬儀の総称であり、特定の形式を指す言葉ではありません。
そのため、家族葬には通夜と告別式を二日間行うケースと、一日葬の形式で行うケースの両方が存在します。
一日葬と家族葬を比較する場合、重要なのは「日程」と「参列者の範囲」という二つの視点です。
一日葬は日程を1日に短縮することに主眼を置いた形式であり、家族葬は参列者を限定することに主眼を置いています。
費用面では、二日間の家族葬よりも一日葬形式の家族葬の方が、通夜関連の費用がかからない分、安くなる傾向にあります。
直葬(火葬式)との費用や内容の違い
直葬(火葬式)は、通夜や告別式といった宗教的な儀式を一切行わず、ごく限られた親族のみで火葬場に集まり、火葬のみを執り行う最もシンプルな形式です。
儀式がないため、費用は20万円前後と、全ての葬儀形式の中で最も安価になります。
一方、一日葬は告別式という儀式をしっかりと行う点が直葬との大きな違いです。
費用は直葬より高くなりますが、故人とのお別れの時間をきちんと設けたい、宗教的な儀礼を大切にしたいと考える場合に適しています。
費用を抑えたいけれど、儀式なしのお別れでは寂しいと感じる方にとって、一日葬は良い選択肢となります。
一日葬の費用をできるだけ抑える3つのコツ
一日葬は比較的費用を抑えられる葬儀形式ですが、いくつかのポイントを押さえることで、さらに葬儀費用を節約することが可能です。
具体的には、葬儀プランの内容を精査すること、利用する斎場を賢く選ぶこと、そして公的な補助金制度を活用することの3点が挙げられます。
これらのコツを実践することで、満足度を下げずに、経済的な負担を軽減したお葬式を実現できます。
不要なオプションを見直してプランを最適化する
葬儀社の提供するプランには、基本的なサービスに加えて様々なオプションが含まれていることがあります。
例えば、祭壇の装花を豪華にしたり、棺のグレードを上げたり、特別な演出を追加したりすると、その分価格は上がります。
費用を抑えるためには、まず見積書の内容を細かく確認し、自分たちにとって本当に必要なものと、なくてもよいものを見極めることが重要です。
故人の遺志や家族の希望を考慮しつつ、見栄を張らずに不要なオプションを外すことで、プランを最適化し、無駄な出費を削減できます。
複数の葬儀社から見積もりを取り、内容と価格を比較検討することも有効な手段です。
費用が安い公営斎場を利用する
斎場の利用料金は、葬儀費用の中でも大きな割合を占める項目の一つです。
斎場には、自治体が運営する「公営斎場」と、民間企業が運営する「民営斎場」の2種類があります。
一般的に、公営斎場は民営斎場に比べて利用料金が安価に設定されています。
さらに、故人または喪主がその自治体の住民である場合には、市民料金が適用され、より費用を抑えることが可能です。
ただし、公営斎場は人気が高く、予約が取りにくい場合があるため、早めに空き状況を確認する必要があります。
費用を重視する場合は、まず公営斎場の利用を検討してみるのが良いでしょう。
自治体や健康保険の補助金制度を活用する
故人が国民健康保険や社会保険に加入していた場合、葬儀を行った人(喪主)に対して補助金が支給される制度があります。
国民健康保険からは「葬祭費」、社会保険からは「埋葬料(費)」という名称で、数万円程度が支給されます。
これらの補助金は、自動的に給付されるものではなく、自分で市区町村の役所や健康保険組合に申請手続きを行う必要があります。
申請には期限が設けられているため、忘れずに手続きを行いましょう。
こうした公的な制度を上手に活用することで、葬儀費用の実質的な負担を軽減させることができます。
費用面だけじゃない!一日葬を選ぶメリット
一日葬が選ばれる理由は、単に費用を抑えられるからだけではありません。
日程が1日で完結することから生まれる、遺族や参列者にとっての様々なメリットが存在します。
特に、心身にかかる負担の軽減や、遠方に住む人が参列しやすくなる点は、大きな利点として挙げられます。
これらのメリットを理解することで、一日葬が自分たちの状況により適した選択肢であるか判断しやすくなります。
遺族や参列者の心身への負担を軽減できる
通夜と告別式を二日間にわたって行う従来のお葬式は、大切な人を亡くした悲しみの中で、遺族が多くの弔問客に対応する必要があり、心身ともに大きな負担となります。
一日葬では、通夜がなくなることで拘束時間が大幅に短縮され、弔問客への対応も告別式の一度に集中します。
これにより、遺族は精神的な落ち着きを保ちやすく、体力的な消耗も少なくて済みます。
特に、高齢の遺族や参列者にとっては、長時間の儀式や移動の負担が軽減されるため、無理なく故人とお別れできるという利点があります。
遠方からの参列者が日帰りで参加しやすい
二日間にわたるお葬式の場合、遠方に住んでいる親族や友人は、参列するために宿泊が必要になることが多く、時間的にも経済的にも負担が大きくなります。
一日葬であれば、告別式から火葬までが1日で終わるため、遠方からでも日帰りで参加することが可能です。
これにより、参列者は宿泊費や仕事を休む日数を気にすることなく、お別れの場に駆けつけやすくなります。
「多くの方に最後のお見送りをしてほしい」と考える遺族にとって、参列のハードルが下がる点は、一日葬の大きなメリットと言えます。
後悔しないために知っておきたい一日葬の注意点
一日葬には多くのメリットがある一方で、比較的新しい形式であるために生じる注意点も存在します。
これらの点を事前に理解し、対策を講じておかなければ、後で「こんなはずではなかった」と後悔につながる可能性もあります。
特に、周囲の人々の理解を得ることや、お別れの時間の捉え方、参列者の都合などについては、慎重に検討する必要があります。
親族や菩提寺の理解を得ておく必要がある
一日葬は、まだ一般的に広く浸透しているとは言えず、親族の中には「お葬式は通夜と告別式を二日間かけて行うもの」という伝統的な考えを持っている方がいるかもしれません。
独断で一日葬に決めてしまうと、後でトラブルに発展する可能性があります。
そのため、なぜ一日葬を選びたいのか、その理由を事前に丁寧に説明し、関係者の理解を得ておくことが非常に重要です。
また、菩提寺がある場合は、その寺院の考え方によっては一日葬での供養を認めてもらえないケースもあります。
必ず事前に住職に相談し、許可を得てから話を進めるようにしましょう。
故人とゆっくりお別れする時間が短くなる
一日葬では通夜を行わないため、必然的に故人と過ごす時間は短くなります。
通夜は、親しい人々が夜通し故人に付き添い、思い出を語り合いながら最後の夜を過ごす、情緒的な意味合いを持つ大切な時間です。
この時間がなくなることで、お別れが慌ただしく感じられたり、心の整理がつきにくかったりする可能性があります。
一日葬を選ぶ際には、この点を家族全員が理解し、納得していることが大切です。
告別式の時間を十分に確保したり、出棺前の時間を大切にしたりするなど、限られた時間の中で心ゆくまでお別れできるよう工夫が求められます。
参列できない人が出てくる可能性がある
一日葬の告別式は平日の日中に行われることが一般的です。
そのため、仕事などの都合で夜に行われる通夜には参列できても、日中の告別式には参加できないという友人や知人が出てくる可能性があります。
特に、故人が会社関係者や地域社会とのつながりが深かった場合、多くの方がお別れの機会を失ってしまうかもしれません。
「通夜があれば弔問に行けたのに」という声が上がることも想定されます。
誰に参列してほしいかをよく考え、主な参列者の都合がつきやすい日程を選ぶなどの配慮が必要になる場合があります。
一日葬は、通夜を行わず告別式から火葬までを1日で執り行うお葬式の形式です。
その費用相場は40万円から60万円程度で、通夜にかかる費用が不要なため、一般葬に比べて経済的負担を大きく軽減できます。
費用面だけでなく、遺族や参列者の心身の負担が少ない、遠方からでも参列しやすいといったメリットがあります。
一方で、親族や菩提寺の理解が必要なことや、お別れの時間が短くなるなどの注意点も存在します。
様々な葬儀の形式の中から最適なものを選ぶには、故人の遺志や家族の状況、予算などを総合的に考慮することが不可欠です。