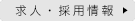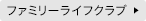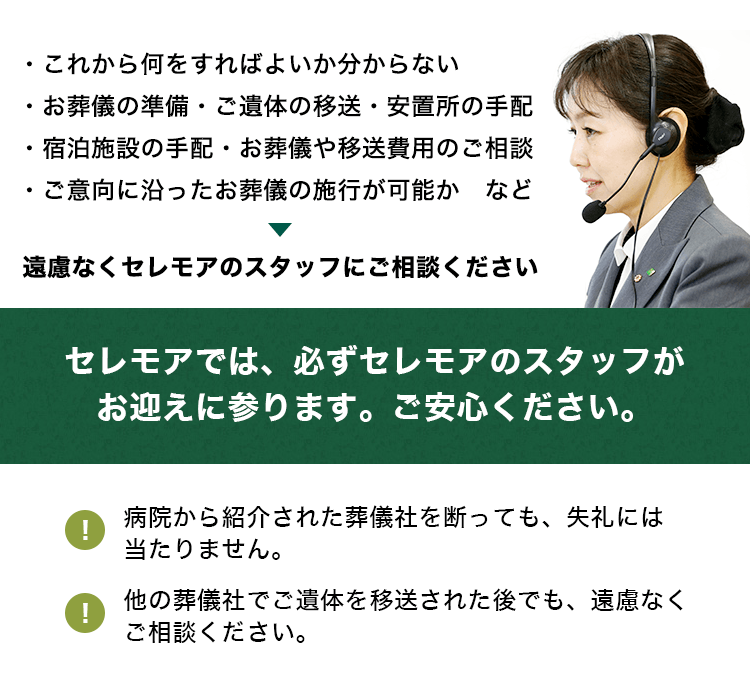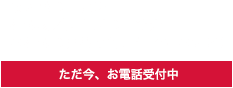一日葬と家族葬の違いとは?葬儀の流れやメリット・デメリットを解説
最終更新:2025-09-30
近年、葬儀の形式は多様化しており、中でも「一日葬」と「家族葬」はよく選ばれる選択肢です。
この二つの言葉は混同されがちですが、その意味するところには明確な違いがあります。
一日葬と家族葬の違いを正しく理解することは、故人や遺族の意向に沿った最適な葬儀を選ぶための第一歩です。
この記事では、それぞれの葬儀形式の基本的な違いから、流れ、費用、メリット・デメリットまでを詳しく比較・解説します。
一日葬と家族葬の基本的な違いを解説
一日葬と家族葬は、それぞれ葬儀を分類する際の視点が異なります。
一日葬が「日程(時間)」に着目した形式であるのに対し、家族葬は「参列者の範囲(規模)」に着目した形式です。
したがって、この二つは対立する概念ではなく、「家族だけで行う一日葬」というように組み合わせることも可能です。
まずは、それぞれの言葉が具体的にどのような葬儀を指すのか、その定義と最も大きな一日葬と家族葬の違いについて解説します。
お通夜を省略するのが「一日葬」
一日葬とは、お通夜を行わず、告別式から火葬までを1日で執り行う葬儀形式です。
本来2日間にわたって行われる儀式を1日に短縮することで、遺族や参列者の身体的・経済的な負担を軽減することを目的としています。
比較的新しい葬儀の形であり、時代のニーズに合わせて広まってきました。
お通夜は省略しますが、告別式という宗教儀式はしっかりと行うため、故人とのお別れの時間は確保されます。
この点で、告別式も行わず火葬のみを執り行う「直葬(火葬式)」とは区別されます。
参列者を限定するのが「家族葬」
家族葬とは、参列者を家族や親族、故人と特に親しかった友人などに限定して行う、比較的小規模な葬儀形式を指します。
参列者の人数に明確な定義はありませんが、一般的には30名程度までで行われることが多いです。
必ずしも家族だけで行う必要はなく、故人や遺族の意向によって呼ぶ範囲を自由に決められます。
義理での参列や一般の弔問客への対応に追われることなく、親しい人たちだけで気兼ねなく、ゆっくりと故人を偲びたいという想いから選ばれることが増えています。
最も大きな違いは「お通夜の有無」
一日葬と家族葬の最も大きな違いは、「お通夜の有無」にあります。
一日葬は、お通夜を省略するという「日程」に関する葬儀形式です。
一方、家族葬は、参列者を限定するという「規模」に関する葬儀形式であり、通常はお通夜と告別式の両方を2日間かけて行います。
このため、両者は異なる視点からの分類であり、「参列者を家族に限定した一日葬」という形式も存在します。
一日葬と家族葬の違いを正しく理解し、それぞれの特徴を把握することが、希望に合った葬儀を選ぶための重要なポイントになります。
一日葬を選ぶ3つのメリット
お通夜を省略して1日で葬儀を終える一日葬には、遺族や参列者にとって多くのメリットがあります。
特に、時間的、身体的、そして経済的な負担を軽減できる点が大きな特徴です。
高齢化社会の進展やライフスタイルの多様化に伴い、負担の少ない葬儀を求める声が高まっていることから、一日葬は注目されています。
ここでは、一日葬を選ぶことで得られる具体的な3つのメリットについて詳しく見ていきます。
遺族の身体的・精神的な負担が軽くなる
従来の葬儀では、お通夜と告別式を2日間にわたって行うため、遺族は長時間にわたり弔問客への対応や儀式の準備に追われます。
特に高齢の遺族にとっては、この2日間の拘束は身体的に大きな負担となりかねません。
一日葬ではお通夜がないため、葬儀が1日で完了します。
これにより拘束時間が大幅に短縮され、身体的な疲労が軽減される点が大きなメリットです。
また、弔問客への対応が1日で済むため、精神的な負担も少なくなり、故人を偲ぶことに集中しやすくなります。
遠方からの参列者の宿泊手配が不要になる
2日間にわたる葬儀の場合、遠方から駆けつける親族や友人は、宿泊場所を確保する必要があります。
遺族が宿を手配するにしても、参列者自身が予約するにしても、手間と費用の両方が発生します。
一日葬であれば、告別式から火葬までが日中に終わるため、遠方の参列者も日帰りが可能になるケースが多くなります。
これにより、参列者は宿泊費の負担がなくなり、遺族も宿泊先を手配する手間を省くことができます。
親族が各地に点在している場合などには、特に大きな利点となるでしょう。
葬儀にかかる費用を抑えられる場合がある
一日葬は、お通夜を行わない分、葬儀に関連する費用の一部を削減できる可能性があります。
具体的には、お通夜の後に参列者へ振る舞う食事(通夜振る舞い)の費用が不要になります。
また、斎場の利用が1日分で済むため、2日間利用する場合に比べて会場費を抑えられることもあります。
ただし、祭壇や棺、火葬料といった葬儀の基本的な費用は変わりません。
そのため、総額が劇的に安くなるわけではありませんが、葬儀社によっては一日葬専用の割安なプランが用意されていることも多く、費用を抑えたい場合の有効な選択肢となります。
一日葬で後悔しないための3つの注意点
多くのメリットがある一日葬ですが、日程を1日に短縮することから生じる注意点も存在します。
これらの注意点を事前に理解し、必要な対策を講じておかないと、後で「こうすればよかった」と後悔することにもなりかねません。
特に、親族や菩提寺への事前相談、参列を希望する方への配慮は、トラブルを避けるために不可欠です。
ここでは、一日葬を選ぶ際に必ず押さえておきたい3つの注意点について解説します。
日程の都合で参列できない人が出やすい
葬儀の日程が1日しかないため、参列を希望していても都合がつかない人が出やすいという注意点があります。
通常の葬儀であれば、お通夜か告別式のどちらかに参列するという選択肢がありますが、一日葬ではその選択ができません。
特に平日の日中に行われる場合、仕事を持つ友人や知人は参列が難しくなる可能性があります。
故人と親しかった方が最後のお別れに来られず、残念な思いをさせてしまうことも考えられるため、誰に参列してほしいかを事前に考え、主要な関係者には日程を早めに相談するなどの配慮が必要です。
葬儀当日のスケジュールが過密になる傾向がある
一日葬は、告別式から火葬、場合によっては初七日法要までを1日で集中的に行うため、当日のスケジュールが非常にタイトになりがちです。
分刻みのスケジュールで進行することもあり、故人との最後のお別れの時間が慌ただしくなってしまい、ゆっくりと偲ぶ余裕がなかったと感じる遺族もいます。
告別式の開式時間が早まったり、火葬場への移動が慌ただしくなったりする可能性もあるため注意が必要です。
葬儀社との打ち合わせの際に、当日の流れを詳細に確認し、時間に少しでも余裕を持たせたスケジュールを組めるか相談することが大切です。
菩提寺から理解を得られない可能性がある
先祖代々のお墓がある菩提寺との関係は、葬儀形式を決める上で非常に重要な注意点です。
仏教の伝統的な教えでは、お通夜と告別式の両方を行うことが正式な作法とされているため、お通夜を省略する一日葬に対して、菩提寺の住職が難色を示す場合があります。
最悪の場合、読経を断られたり、その後の納骨を受け入れてもらえなかったりするトラブルに発展する恐れもあります。
菩提寺がある場合は、必ず葬儀形式を決める前に相談し、一日葬で行いたい旨を伝えて許可を得ておくことが不可欠です。
家族葬を選ぶ3つのメリット
参列者を家族や親しい人に限定して行う家族葬は、故人との最後の時間を大切にしたいと考える方々に選ばれています。
一般葬のような儀礼的な対応に追われることなく、アットホームな雰囲気の中で故人を偲ぶことができるのが最大の魅力です。
精神的な負担が少ないだけでなく、故人らしさを反映した自由な形式を選びやすいという利点もあります。
ここでは、家族葬ならではの3つの具体的なメリットを詳しく解説します。
親しい人だけで故人とのお別れに集中できる
家族葬の最大のメリットは、参列者が家族やごく親しい間柄の人に限られるため、心置きなく故人とのお別れに集中できる点です。
一般葬では、会社関係者や近所の方など、義理で参列する方への挨拶や対応に多くの時間と気を遣う必要があります。
家族葬ではそうした儀礼的な対応がほとんどないため、その分の時間を故人との思い出を語り合ったり、家族だけで悲しみを分かち合ったりするために使えます。
アットホームな雰囲気の中で、気兼ねなく最後のお別れができることは、遺族にとって大きな心の支えになります。
参列者への挨拶など気遣いの負担が少ない
大規模な葬儀では、遺族は多くの弔問客一人ひとりに対して挨拶を行い、香典の管理や返礼品の準備など、様々な対応に追われます。
これは精神的にも身体的にも大きな負担です。
家族葬では参列者が限定されているため、こうした形式ばった挨拶や過度な気遣いの必要がありません。
受付業務や会食の準備といった物理的な負担も大幅に軽減されます。
精神的な余裕が生まれることで、遺族は心穏やかに故人を送り出すことに専念しやすくなります。
家族だけで静かに見送りたいと考える場合に最適です。
宗教儀礼にとらわれない自由な形式を選びやすい
家族葬は参列者が身内に限られるため、世間体を気にすることなく、故人や遺族の意向を反映させやすいというメリットがあります。
伝統的な宗教儀礼に厳密に従う必要はなく、無宗教形式での葬儀を選択することも可能です。
例えば、故人が好きだった音楽を生演奏で流したり、思い出の写真や愛用品を飾るスペースを設けたりと、オリジナリティあふれる演出で故人らしいお別れの会を実現できます。
家族だけだからこそ、形式にとらわれず、温かみのある自由な葬儀を執り行いやすいのです。
家族葬で後悔しないための3つの注意点
故人とゆっくりお別れができる家族葬ですが、参列者を限定するという特性上、いくつか注意すべき点があります。
特に、葬儀にお呼びしなかった方々への配慮や、親族間の意見のすり合わせは、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。
これらの注意点を事前に理解し、適切な対応を準備しておくことで、心残りなく故人を見送ることができます。
ここでは、家族葬を執り行う際に気をつけたい3つのポイントを解説します。
葬儀後に自宅への弔問客が増えることがある
家族葬を行った場合、葬儀に参列できなかった友人や知人、会社関係者などが、後日になって個別に自宅へ弔問に訪れるケースが少なくありません。
葬儀が終わり、少し落ち着きたいと考えている時期に、入れ替わり立ち替わり弔問客の対応に追われることになり、かえって遺族の負担が増えてしまう可能性があります。
その都度、挨拶やお茶出し、香典返しの手配などが必要になるため、この点は注意点として念頭に置くべきです。
弔問を辞退する旨を事前に明確に伝えるか、後日お別れの会を設けるなどの対策が考えられます。
親族間で葬儀形式について意見が分かれる場合がある
家族葬という言葉が広く知られるようになった現在でも、親族の中には「葬儀は広く知らせて、多くの方に見送ってもらうべきだ」という伝統的な考えを持つ方もいます。
特に年配の親族からは、参列者を限定することに対して理解が得られず、反対される可能性があります。
故人の遺志であっても、事前の相談なしに家族葬を進めてしまうと、親族間にしこりを残す原因になりかねません。
なぜ家族葬を選びたいのか、故人の想いはどうだったのかを丁寧に説明し、主要な親族の合意を得ておくことが、トラブルを避けるための重要な注意点です。
訃報を知らせる範囲や伝え方に配慮が必要になる
家族葬を行う上で、誰にまで訃報を知らせ、どのように伝えるかは非常にデリケートな問題です。
連絡をしなかったことで、故人と親しかった方が「最後のお別れをしたかった」と悲しんだり、「知らせてくれなかった」と不快に感じたりする可能性があり、その後の人間関係に影響を及ぼす注意点です。
訃報を伝える際には、家族葬で執り行うため参列はご遠慮いただく旨を明確に、かつ丁寧に伝える必要があります。
一般的には葬儀後に報告することが多いですが、相手との関係性を考慮し、知らせるタイミングや伝え方を慎重に判断することが求められます。
【比較】一日葬と家族葬の当日の流れ
一日葬と家族葬では、お通夜の有無によって葬儀全体の流れが大きく異なります。
それぞれの形式が、自分たちの体力的な状況や故人との別れに対する考え方に合っているかを見極めるためには、当日の具体的なスケジュールを把握しておくことが役立ちます。
どちらの形式を選ぶかによって、遺族や参列者の拘束時間も変わってきます。
ここでは、一日葬と家族葬の一般的な当日の流れをそれぞれ紹介し、その違いを比較します。
告別式から火葬までを1日で行う一日葬の流れ
一日葬の当日の流れは、まず遺族や親族が斎場に集合し、故人を棺に納める「納棺の儀」から始まります。
その後、告別式が開式され、僧侶による読経、弔辞の奉読や弔電の紹介、参列者による焼香などが進められます。
告別式が閉式すると、故人との最後の対面として、棺の中に花を手向ける「お花入れの儀」が行われ、棺の蓋が閉じられます。
そして、霊柩車で火葬場へ出棺し、火葬が終わるのを待ってから、遺骨を骨壷に収める「お骨上げ」を行い、一連の流れが終了となります。
お通夜と告別式を2日間かけて行う家族葬の流れ
家族葬の一般的な流れは、2日間かけて行われます。
1日目の夕方からお通夜が始まり、参列者が集まった後、僧侶による読経や焼香が行われます。
お通夜の後には、故人を偲びながら食事をする「通夜振る舞い」の席が設けられるのが通例です。
2日目の日中には告別式が執り行われます。
告別式の流れは一日葬とほぼ同じで、読経や焼香、お花入れの儀を経て火葬場へ出棺します。
火葬、お骨上げの後、地域や宗派によっては初七日法要を繰り上げて行う「繰り上げ法要」や、会食の席である「精進落とし」が行われることもあります。
一日葬と家族葬の費用相場を比較
葬儀の形式を選ぶ際、費用がどのくらいかかるのかは、誰もが気になる重要なポイントです。
一日葬と家族葬では、儀式の内容や日数、参列者の規模が異なるため、費用の相場にも差があります。
ただし、葬儀費用は祭壇のグレードやオプション、地域によっても大きく変動するため、ここで示す相場はあくまで一般的な目安として捉えることが大切です。
それぞれの費用の内訳や特徴を理解し、自分たちの予算と照らし合わせて検討しましょう。
一日葬にかかる費用の目安
一日葬にかかる費用の相場は、40万円から100万円程度が目安です。
この費用には、斎場の使用料、祭壇、棺、遺影、寝台車・霊柩車、火葬料、人件費などが含まれます。
お通夜を行わないため、通夜振る舞いの飲食接待費や、2日分の会場費がかからず、一般的な二日葬に比べて費用を抑えやすい傾向にあります。
ただし、参列者の人数に応じた返礼品の費用は別途必要になることが多いです。
葬儀社によってプラン内容や料金体系は様々なので、複数の社から見積もりを取り比較することが賢明です。
家族葬にかかる費用の目安
家族葬にかかる費用の相場は、参列者の人数にもよりますが、一般的に50万円から120万円程度とされています。
家族葬は葬儀の規模を表す言葉であり、お通夜と告別式を2日間かけて行うのが基本のため、一日葬よりも費用は高くなる傾向があります。
費用の内訳は一日葬とほぼ同じですが、通夜振る舞いの飲食費や2日間の会場費などが加わります。
参列者の人数が費用を左右する大きな要素ですが、少人数であれば小さな式場を選んだり、返礼品の数を抑えたりすることで、費用を調整することも可能です。
希望の規模と内容を葬儀社に伝えて、詳細な見積もりを作成してもらうことが重要です。
【状況別】あなたに合うのは一日葬?それとも家族葬?
ここまで、一日葬と家族葬の違いやそれぞれのメリット・デメリット、費用などを解説しました。
これらの情報を踏まえて、最終的にどちらの形式が自分たちの状況に合っているのかを判断する必要があります。
葬儀の選択に絶対的な正解はなく、故人の遺志や遺族の体力、経済状況、価値観などを総合的に考慮して決めることが大切です。
ここでは、どのような方にどちらの葬儀形式がおすすめかを、具体的な状況別に提案します。
体力的な負担や費用をできるだけ減らしたい方は一日葬
遺族が高齢である、あるいは遠方に住んでいて、2日間にわたる長時間の拘束が体力的に厳しい場合には、1日で完結する一日葬が適しています。
また、葬儀にかかる費用を少しでも抑えたいと考えている場合も、通夜振る舞いなどの費用を削減できる一日葬は有力な選択肢です。
仕事の都合などで遺族が長く休みを取れない場合や、参列者の多くが日帰りを希望する場合にも、一日葬は理にかなっています。
ただし、菩提寺への事前相談など、クリアすべき注意点があることも忘れてはなりません。
時間をかけて丁寧にお別れをしたい方は家族葬
義理の弔問や世間体を気にすることなく、ごく内輪の親しい人たちだけで故人を囲み、心ゆくまで最後の時間を過ごしたいと願う方には、家族葬が最も適しています。
お通夜から告別式まで2日間あることで、故人との思い出をゆっくりと語り合い、悲しみを分かち合う時間を十分に確保できます。
また、宗教的な形式にとらわれず、故人の好きだった音楽を流すなど、オリジナリティのある温かいお別れの場を創りたい場合にも、家族葬は最適です。
家族だけで故人を偲ぶことに集中したいという気持ちを何よりも大切にしたい場合に選ぶとよいでしょう。
一日葬と家族葬は、それぞれ「日程の短縮」と「規模の限定」という異なる特徴を持つ葬儀形式です。
一日葬は、お通夜を省略して1日で執り行うことで、遺族の身体的・経済的負担を軽減するメリットがありますが、お別れの時間が短くなるなどの注意点も存在します。
一方、家族葬は、参列者を限定することで、親しい人だけで故人とのお別れに集中できる利点がありますが、葬儀後の弔問対応などへの配慮が求められます。
両者の違いとそれぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、故人の遺志や遺族の状況に最も適した葬儀の形を選択することが重要です。