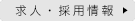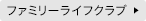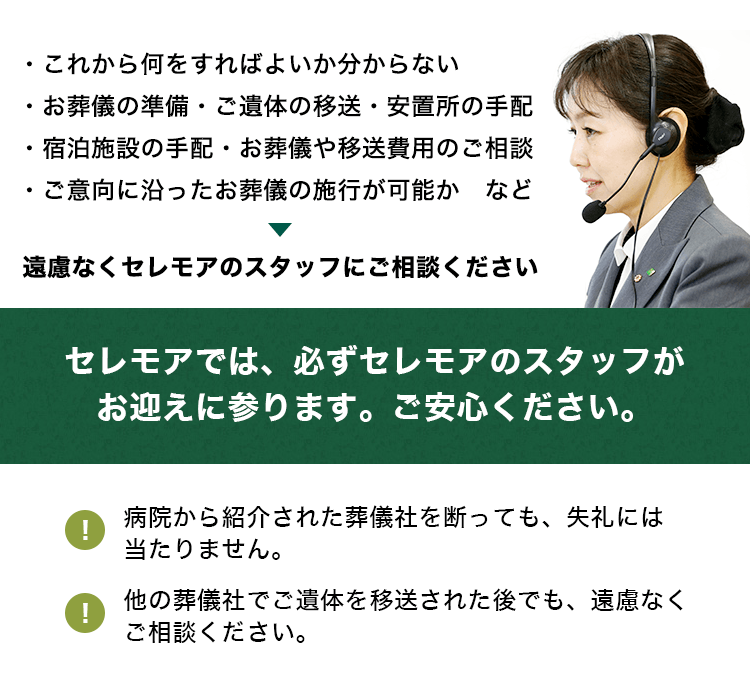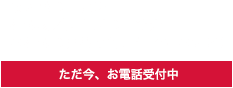火葬式のメリット・デメリットとは?費用や流れ、注意点を解説
最終更新:2025-10-31
火葬式とは、通夜や告別式といった宗教的な儀式を省略し、ごく限られた親族のみで火葬を行う、最もシンプルな葬儀形式です。
この記事では、火葬式のメリット・デメリットをはじめ、費用相場や当日の流れ、後悔しないための注意点について詳しく解説します。
経済的な負担を抑えたい方や、参列者の高齢化を考慮している方、また特定の宗教・宗派にとらわれない無宗教の形で見送りたい方など、さまざまな理由から火葬式を検討する際に役立つ情報を提供します。
火葬式とは?通夜や告別式を行わないシンプルな葬儀形式
火葬式は、通夜や葬儀・告別式といった儀式を行わず、ごく親しい家族や親族のみで火葬場へ向かい、故人を見送る葬儀形式です。
参列者の人数は限定的で、一般的には数名から10名程度、場合によっては喪主と近親者の2人だけで執り行うケースもあります。
ご逝去後、法律で定められた24時間が経過した後に、ご遺体を安置場所から直接火葬場へ搬送し、火葬炉の前で最後のお別れをします。
儀礼的な弔問対応や会食などがないため、費用面や遺族の身体的・精神的な負担を大幅に軽減できることから、近年選択する人が増えています。
火葬式を選ぶことで得られる3つのメリット
火葬式は、費用や時間の面で多くの利点がある葬儀形式です。
通夜や告別式を行わないため、葬儀全体の費用を大幅に削減できるだけでなく、準備や参列者対応にかかる遺族の身体的・精神的な負担も軽減されます。
また、ごく少人数で静かに故人を見送れるため、親しい人だけで心ゆくまでお別れの時間を過ごしたいと考える方にも適しています。
ただし、これらのメリットを最大限に活かすためには、火葬式特有のデメリットについても事前に理解しておくことが不可欠です。
メリット1:葬儀にかかる費用を大幅に抑えられる
火葬式の最大のメリットは、葬儀費用を大幅に抑えられる点です。
一般的な葬儀で大きな割合を占める、通夜や告別式のための式場使用料、祭壇の費用、会葬者への返礼品代、飲食接待費などが一切かかりません。
葬儀社に支払う費用は、ご遺体の搬送や安置、棺、骨壷、火葬手続きの代行など、火葬に必要な最低限のサービスに限定されます。
そのため、一般的な葬儀の費用相場が100万円を超えることもあるのに対し、火葬式は20万円から40万円程度で執り行うことが可能です。
経済的な事情で大きな費用をかけられない場合や、故人が生前から質素な見送りを希望していた場合に適した選択肢となります。
メリット2:遺族の身体的・精神的な負担を軽減できる
遺族の身体的・精神的な負担が少ないことも、火葬式の大きなメリットです。
通夜や告別式を行わないため、葬儀の準備に要する時間や労力が大幅に削減されます。
遠方に住む親族が何度も足を運ぶ必要がなくなり、高齢の遺族にとっても負担が軽くなります。
また、多くの弔問客への挨拶や気遣いといった精神的な負荷からも解放されます。
大切な人を亡くした直後で心身ともに疲弊している遺族にとって、儀礼的な対応に追われることなく、静かに故人を偲ぶ時間に集中できる点は、大きな利点と言えます。
故人との最期の時間を穏やかに過ごしたいと願う遺族にとって、心身の負担を最小限に抑えられる葬儀形式です。
メリット3:短時間・少人数で静かに故人を見送れる
火葬式は、ごく近しい家族や親族など、本当に親しかった人たちだけで故人を見送ることができる葬儀形式です。
参列者が限定されるため、儀礼的な挨拶や対応に時間を費やすことなく、故人との最後の時間を静かに、そして深く過ごすことが可能です。
一般的な葬儀のように多くの参列者に囲まれることなく、プライベートな空間で心ゆくまでお別れができます。
葬儀全体の所要時間も、ご逝去から火葬・お骨上げまで含めて短期間で完了します。
現代の多様化する家族の形や、人間関係のあり方に合った、シンプルで心のこもった見送りを実現できる方法の一つです。
火葬式を選ぶ前に知っておきたいデメリット
火葬式は費用や負担を軽減できる一方で、いくつかのデメリットも存在します。
儀式を簡略化するため、故人とお別れする時間が非常に短くなることは避けられません。
また、伝統的な葬儀の形を重んじる親族や周囲の人々から、理解を得られない可能性も考慮する必要があります。
これらのデメリットを事前に把握し、対策を講じなければ、後々トラブルに発展したり、心残りになったりする恐れがあります。
火葬式を決定する前には、これから挙げる点を慎重に検討することが重要です。
故人とお別れする時間が短くなる
火葬式では通夜や告別式を行わないため、故人とゆっくりお別れをする時間が短くなります。
ご遺体は安置施設に直接搬送されることが多く、面会時間が限られている場合や、そもそも面会ができない施設もあります。
お別れができるのは、主に納棺の際と、火葬場で火葬炉に納められる直前のわずかな時間だけです。
そのため、もっと顔を見ておきたかった、もっと話しかけたかったという心残りが生じる可能性があります。
特に、突然の別れで心の整理がついていない場合、お別れの時間が短いことが、後々大きな後悔につながることも考えられます。
十分な時間をかけて故人を偲びたいと考える方にとっては、慎重な判断が求められます。
親族や周囲の理解が得られない可能性がある
火葬式はまだ新しい葬儀の形であり、特に年配の親族や地域の慣習を重んじる方々からは「通夜や告別式を行うのが当然」という考えが根強い場合があります。
そのため、火葬式で済ませることに対して「故人がかわいそうだ」「弔う気持ちが足りない」といった反対意見や批判を受ける可能性があります。
事前の相談なく決定してしまうと、親族間で深刻なトラブルに発展し、その後の関係にまで影響を及しかねません。
なぜ火葬式を選んだのか、故人の遺志であったのか、あるいは経済的な事情などを丁寧に説明し、一人ひとりの理解を得る努力が不可欠です。
周囲の理解を得られないまま進めることは、大きなリスクを伴います。
後日、弔問客への個別対応が必要になる場合がある
火葬式で葬儀を執り行った場合、葬儀に参列できなかった友人や知人、会社関係者などが、後日自宅へ弔問に訪れることがあります。
その都度、個別に弔問客を迎え、お茶出しや挨拶などの対応をする必要が生じます。
これが頻繁になると、結果的に葬儀後の遺族の負担が増加してしまう可能性があります。
また、それぞれの方から香典をいただいた場合の返礼品の準備も必要です。
葬儀を簡素化したつもりが、かえって長期間にわたって来客対応に追われることになりかねません。
こうした事態を避けるためには、死亡通知を送る際に、火葬式で葬儀を執り行った旨と、弔問や香典を辞退する旨を明確に伝えておくといった配慮が求められます。
菩提寺に納骨できないケースがある
先祖代々のお墓がある菩提寺に納骨を考えている場合、火葬式を選ぶ際には特に注意が必要です。
寺院によっては、通夜や告別式といった宗教儀式を執り行うことを納骨の条件としている場合があります。
読経や戒名の授与といった儀式を経ていない遺骨は受け入れられない、という考えを持つ住職も少なくありません。
菩提寺に何の相談もなく火葬式を済ませてしまうと、いざ納骨しようとした際に断られてしまうという深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
最悪の場合、納骨先を新たに探さなければならなくなります。
菩提寺がある場合は、必ず葬儀の形式を決定する前に住職へ連絡し、火葬式で進めたい意向を伝えて許可を得ることが不可欠です。
火葬式当日の一般的な流れ
火葬式は一般的な葬儀とは異なり、シンプルな流れで進みます。
ご逝去されてから葬儀社に連絡し、ご遺体の安置、打ち合わせを経て、火葬当日を迎えるのが一連のプロセスです。
通夜や告別式がないため、準備期間も短く、精神的・身体的な負担が少ないのが特徴です。
しかし、いざという時に慌てないためにも、ご逝去からお骨上げまでの具体的なステップを事前に把握しておくことは大切です。
ここでは、火葬式当日の一般的な流れを順を追って解説します。
ステップ1:ご逝去後、ご遺体を安置場所へ搬送する
病院や施設で亡くなられた場合、最初に行うのがご遺体の搬送です。
法律により死後24時間は火葬することが禁じられているため、火葬の日までご遺体を安置しておく場所が必要になります。
すぐに葬儀社へ連絡し、寝台車でご自宅か斎場の安置施設などへ搬送してもらいます。
自宅での安置が難しい場合は、葬儀社が提携している専用の安置施設を利用するのが一般的です。
この搬送と安置の手配が、ご逝去後、遺族が最初に行うべき具体的な手続きとなります。
どの葬儀社に依頼するかをあらかじめ決めておくと、この段階でスムーズに行動できます。
ステップ2:葬儀社と火葬の日程などを打ち合わせる
ご遺体の安置が完了したら、葬儀社の担当者と具体的な打ち合わせを行います。
この場で、火葬を行う日時と火葬場を正式に決定します。
火葬場の空き状況を確認しながら、遺族の希望に沿った日程を調整します。
同時に、火葬式プランの内容の再確認や、費用の見積もり、喪主の決定など、詳細を詰めていきます。
また、役所への死亡届の提出や火葬許可証の申請といった、煩雑な行政手続きも葬儀社が代行してくれるのが一般的です。
この打ち合わせで葬儀の全体像が確定するため、不明点や要望があれば遠慮なく担当者に伝え、疑問を解消しておくことが重要です。
ステップ3:ご遺体を棺に納める(納棺の儀)
火葬の日時が確定した後、出棺前に「納棺の儀」を執り行います。
これは、ご遺体を清め、死装束を着せて棺に納める儀式です。
通常は葬儀社のスタッフである納棺師が専門的な知識と技術をもって行いますが、遺族も立ち会い、手伝うことが可能です。
この際に、故人が生前に愛用していた品物や手紙などを「副葬品」として一緒に棺へ納めることもできます。
ただし、燃えにくい素材のものは入れられないため、事前に葬儀社に確認が必要です。
納棺の儀は、故人と対面できる最後の時間となることが多く、ゆっくりとお別れをするための非常に大切な儀式です。
安置場所やプランによっては、この儀式を行わない場合もあります。
ステップ4:火葬場へ出棺し、火葬・お骨上げを行う
火葬当日、納棺されたご遺体は霊柩車で火葬場へと搬送されます(出棺)。
火葬場に到着すると、火葬炉の前に棺を安置し、最後のお別れをします。
この時、僧侶を呼んで簡単な読経(炉前読経)をしてもらうことも可能です。
告別を終えると、棺は火葬炉に納められ、火葬が始まります。
火葬にかかる時間は1時間から2時間程度で、その間、遺族は控室で待機します。
火葬が終わると、遺骨を骨壷に収める「お骨上げ(収骨)」を行います。
近親者で箸を使い、遺骨を拾い上げて骨壷に納めていきます。
このお骨上げをもって、火葬式の一連の儀式はすべて終了となります。
火葬式にかかる費用の相場と主な内訳
火葬式にかかる費用の全国的な相場は、20万円から40万円程度が目安です。
ただし、この金額は地域や依頼する葬儀社、プラン内容によって変動します。
費用の主な内訳としては、ご遺体の搬送料(寝台車)、ご遺体の安置費用、ドライアイス代、棺、骨壷、そして火葬料金などが挙げられます。
このほか、役所の手続きを代行する費用や、運営スタッフの人件費も含まれます。
注意すべき点は、提示されているプラン料金に何が含まれているかです。
例えば、安置日数が規定を超えた場合の追加料金や、火葬場の使用料が別途必要になるケースもあります。
必ず複数の葬儀社から見積もりを取り、内訳を詳細に比較検討することが重要です。
後悔しないために|火葬式を検討する際の注意点
火葬式は費用を抑えられ、遺族の負担も少ないというメリットがありますが、その手軽さだけで安易に決定すると、後悔につながる可能性があります。
特に、親族や菩提寺との関係性、そして葬儀社との契約内容については、慎重な確認が不可欠です。
これらの点を疎かにすると、後々トラブルに発展したり、「もっとこうすればよかった」と感じたりする原因になります。
ここでは、火葬式を選んで後悔しないために、事前に押さえておくべき重要な注意点を3つに絞って解説します。
親族には事前に相談し理解を得ておく
火葬式を執り行うことを決める前に、必ず親族、特に故人と関係の深い方々へ相談し、理解を得ておくことが極めて重要です。
「通夜や告別式をしない」という形式に、抵抗を感じる親族がいる可能性は十分に考えられます。
なぜ火葬式という選択をしたのか、その理由(故人の遺志、経済的な事情など)を誠実に、そして丁寧に説明する姿勢が求められます。
事後報告になったり、相談なく決定したりすると、「故人をないがしろにされた」と感じる人が現れ、親族間に深刻なしこりを残す原因になりかねません。
事前に話し合いの場を設け、合意形成を図ることで、無用なトラブルを避け、円満に故人を見送ることができます。
菩提寺がある場合は必ず連絡する
先祖代々のお墓がある菩提寺との関係は、火葬式を検討する上で最も注意すべき点の一つです。
菩提寺があるにもかかわらず、何の連絡もせずに火葬式を執り行ってしまうと、納骨を断られるという重大な問題に発展する可能性があります。
寺院の考え方によっては、通夜や告別式といった宗教儀礼を経ていない遺骨の受け入れを認めていない場合があるためです。
このような事態を避けるため、火葬式を検討している段階で、必ず菩提寺の住職に連絡を取りましょう。
火葬式で故人を送りたいという意向を伝え、納骨が可能かどうかを確認し、許可を得ておくことが不可欠です。
事前の相談が、菩提寺との良好な関係を維持し、納骨先を失うリスクを回避することにつながります。
葬儀社のプラン内容をしっかり確認する
葬儀社が提示する「火葬式プラン」は、会社によって含まれるサービス内容や料金設定が大きく異なります。
「プラン料金一式」と書かれていても、実際には最低限の内容しか含まれておらず、後から追加費用が次々と発生するケースも少なくありません。
例えば、ご遺体の搬送距離に制限があったり、安置日数が決まっていたり、ドライアイスの追加が別途料金だったりすることがあります。
契約前には必ず見積書を取り、どのサービスがプランに含まれ、何がオプション(追加料金)になるのかを項目ごとに詳細に確認しましょう。
複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較検討することで、費用に関するトラブルを防ぎ、納得のいく葬儀社を選ぶことができます。
火葬式は、通夜や告別式を省略することで、葬儀費用を大幅に抑え、遺族の身体的・精神的な負担を軽減できるという大きなメリットがあります。
少人数で静かに故人を見送りたいと考える方にとって、適した葬儀形式です。
しかしその一方で、故人とのお別れの時間が短くなる、親族や菩提寺の理解が得られにくいといったデメリットも存在します。
後悔のない見送りをするためには、これらのメリットとデメリットの両方を正しく理解することが不可欠です。
そして、最も重要なのは、親族や菩提寺といった関係者へ事前に丁寧に相談し、合意を得ておくことです。
葬儀社のプラン内容を吟味することも含め、慎重に準備を進める必要があります。